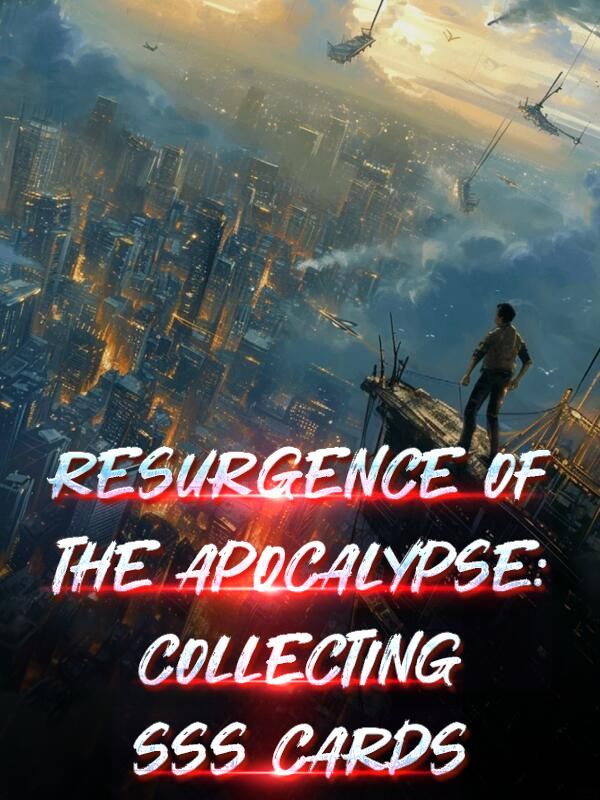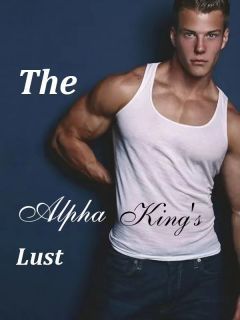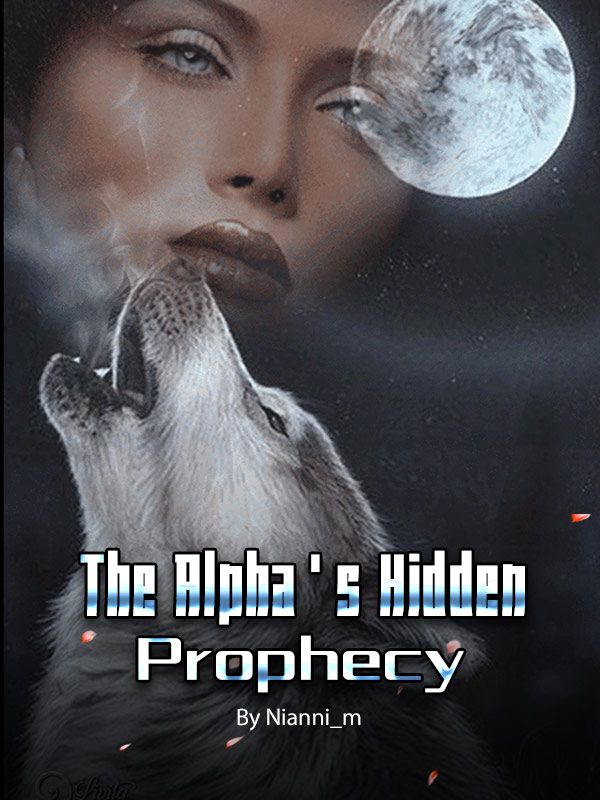彼の分厚い手が、彼女の太ももの内側のラインに沿って、少しずつ優しくなぞる。指がするすると上に移動し、濡れた部分に触れて、彼女の柔らかいところを探り、そこで止まる。彼は躊躇しているのがわかるけど、彼女は彼の青い海のような瞳を見つめながら、笑顔で彼を促す。彼の手を取り、もっと奥へと誘い、彼の大きな指が彼女の中に入った瞬間、彼女は目覚めた。
「クソッ!」 ケイトリン は叫び、目をこすって眠気を払う。いつもこんな夢を見るけど、いつも途中で終わってしまうことに首をかしげる。大抵はもっと奥までいくし、時々現実みたいに感じることだってあるのに。
起き上がって、時間を確認する。「最悪!もうこんな時間。」と、ケイトリン はつぶやきながら、パリッとしたエジプト綿のシーツから足を出す。数ヶ月前に落ち込んでいた時に、自分へのご褒美として買ったものだ。
当時の ボーイフレンド は、彼女が浮気されていたことがわかって、彼女を振ったばかりだった。それで、彼女はブランニガンズに行ってそれを買ったんだ。彼女の予算からすると、ちょっと高かったけど、「まあいいや」と彼女は思った。だって、彼女は当時「人生の愛」と思っていたものを失ったばかりなんだから。
シーツから抜け出し、慌てて着替えてシャワーはパス。でも、ドアから飛び出す前に、冷めたコーヒーと古くなったドーナツを掴んだ。自分の車に着くと、ドーナツとコーヒーカップを車の屋根に置き、ポケットに手を入れて鍵を探る。
鍵を取り出すと、ほとんど落としそうになる。「ついてないな。」と、ケイトリンは独り言を言いながら車のロックを解除し、屋根の上に危うく置いたままのドーナツとコーヒーを忘れそうになる。シートベルトをしてエンジンをかけると、一口飲んで吐きそうになる。おかしい、昨日はこんなにまずいコーヒーだったかなんて覚えてないのに。
道を走っていると、窓を開けてコーヒーを捨てた。すぐ近くの私道に止まっているパトカーにギリギリ当たらないように。サイレンを鳴らしながらパトカーが後ろに迫ってくるのが聞こえて、彼女はスピード違反をしていたことに気づく。「マジかよ。今朝は他に何が起こるんだ?」と、ケイトリン は目を回しながら、止まる。
ミシガン州ミッドランドの警察官が彼女の開いた窓に近づいてきて、「奥さん、制限速度を10キロオーバーしていたのをご存知ですか?」と尋ねた。彼女は彼をちらりと見て、彼がかっこいいことに気づく。
彼の体つきを見て、10段階評価で8.5と判断。彼の長い栗色の髪と、夏の日に焼けたような肌。背の高い男性にしては筋肉質で、彼の青い瞳は最高。制服が似合っていないので、彼の残りの部分はあまりよく見えない。
見上げると、青い瞳が期待を込めて彼女を見つめ、彼女は口を開くが、言葉は出てこない。代わりに、彼女は泣き出し、涙を隠すために顔を背ける。彼は優しく彼女の肩に手を置き、静かに言った。「大丈夫?そんなに悪いことじゃないよ。」
彼女は彼と正面から向き合い、涙ながらに「もう最悪な朝だったんです。アラームが鳴らなくて寝坊したし、今度は仕事に遅刻するし。社長は私がドアをくぐった瞬間に私をクビにするでしょう。」と話す。まつげをパタパタさせながら、「 オフィサー 、スピードに気をつけるべきだったのに、すみません。」と続けた。
彼は優しく彼女を見て、微笑んだ。「奥さん、もしあなたが笑顔を見せて元気を出してくれるなら、今朝あなたを見たことは忘れましょう。きっとあなたが思っているほど悪くないですよ。だって、あなた、私に会えたんだから。」
「実は、私が最近経験している一連の悪い日の、ただのの一日なんです。私の運は最近ちょっと低迷しているみたいだけど、あなたの優しさを見て、すべての男がクソ野郎ってわけじゃないってことがわかりました。」と、彼女は口元に微笑みを浮かべながら言った。
フロントウィンドウから外を見ると、雨が降りそうだ。「最悪!土砂降りになりそう。」彼が考えを変えないように、彼女は口を閉じた。
彼は彼女を上から下まで見て、彼女がいかに美しいかに気づき、彼女の白い肌に長い金髪、親しみやすいヘーゼルの瞳は、彼を彼女と一緒に後部座席に潜り込みたいと思わせたので、ある考えが浮かんだ。彼女を見つめながら、彼は心の中で考えた、「彼女は身長160センチしかないように見える。後部座席に簡単に入りそうだし、彼女の豊かな胸が私の枕と同じくらい柔らかいかどうか確かめられるかもしれない。」
「奥さん、お名前を教えていただけますか?」彼は親切な青い瞳で彼女を見つめ、遠くの稲妻に目をやった。
「私の名前は ケイトリン・ランドール です。運転免許証と登録証を渡す必要がありますか?」彼は彼女の方を向き、今すぐ中に入って、結局自分が正しいかどうか確かめたいという考えが頭から離れないことを認めた。
「いや、 ケイトリン 。ただあなたの電話番号が欲しいだけなんだ。僕の名前は ジョン だ。」彼は握手を差し出し、微笑みながら続けた。「会えて嬉しいよ。」顔を赤らめながら、彼は彼女が教えてくれることを願った。
「いいわよ。あなたの番号を教えてもらったら、すぐにテキストを送るわね?それを使って、連絡先を保存できるわ。」彼女は彼の返事を待った。
「ああ、問題ないよ。」
彼が番号を教えると、彼女はそれを入力し、「こんにちは」というメッセージを送信し、送信ボタンを押した。彼の携帯電話が鳴り始めると、彼の顔が明るくなった。稲妻が再び落ちる前に、彼はすぐにそれをつかみ、「こんにちは」と打ち込み、送信した。
「すごい。ありがとう、 ケイトリン 、番号を教えてくれて。今週末にデートでテキストしてもいい?」彼はものすごく気まずそうに彼女の返事を待った。
「ええ、問題ないわ。楽しみにしてるわ。でも、チケットを切るつもり?もしそうじゃないなら、急いだほうがいいわ。ものすごく危険になりそうだから。」
彼は稲妻を見上げ、それから彼女を見た。「もちろん、そんなことしないよ。君が経験した朝の後では、チケットは切れないよ。これは警告だと思って、もっと気をつけてくれ。」彼は満面の笑みを浮かべ、別れの挨拶をした。
彼女は唇を舐め、ため息をついて答えた。「本当にありがとう。やっとこの日はよくなってきたわ。こんなにイケメンな人に止められて、チケットも切られずに電話番号を聞かれるなんて、滅多にないことだわ。本当にありがとう。」
「どういたしまして。今夜連絡くれるかな?」彼女の答えを待ちながら、彼は歩き回り、彼女が同意すると、彼に微笑んだ。
彼女にうなずき、稲妻が危険なほど近くに落ちたので、彼は自分の車に駆け戻った。彼がいなくなったことに安堵し、彼が彼女に番号を尋ねてくれたことにいくらか興奮しながら、彼女は座席に座り、車を始動させた。彼が車から出て彼女の前を通り過ぎるときに手を振り、彼女は少しの間そこに座って落ち着いてから、車線を戻った。会社に着くまでに、完全に2時間遅刻し、彼女は静かに自分の机に向かった。
「ランドールさん、コミュニケーションに問題があるようです。私のオフィスに来てもらえますか?」 ミスター・コーエン が立ち止まり、不満げな顔で彼女に尋ねた。
「はい、先生。まず、自分のものを引き出しに入れてもいいですか?」
彼女が引き出しを開け始めると、彼は振り向き、「必要ありません。あなたはもうここにいないからです。今、私のオフィスに来てください。」と告げた。その瞬間、彼女は終わりだと悟り、彼のオフィスについていき、革張りの椅子に座った。
「さて、 ランドール さん。ご存知の通り、私はあなたに何度も遅刻しないようにと言いました。今日は我慢の限界です。言い訳は聞きたくありません。最終小切手と退職金をお渡しします。これらを受け取って、机から自分のものを持って出て行ってください。」彼は彼女に封筒を手渡した。
彼女は顔に無表情を浮かべながらパニックになる。「 ランドール さん、聞こえましたか?もう終わりです。出て行っていいですよ。」
彼女は顔を上げると、彼の顔に嘲笑が浮かんでいた。彼の醜い笑顔が彼女に嫌な気分を与えたので、何か言いそうになったが、やめた。「ありがとう、 ミスター・コーエン 。あなたのもとで働くのは楽しかったわ。」そう言って、彼女は立ち上がり、部屋を出た。
自分の机に戻ると、彼女は自分の私物を集め、同僚に別れを告げた。「 ジャネット 、本当に寂しくなるわ。あなたのおかげで、ここで働くのは楽しい経験になったわ。もっとお互いを知ることができなかったのが残念よ。いつか私に電話してくれて、一緒に遊んだりできるかもね。」 ケイトリン は ジャネット の肩に手を置き、振り向いて ケイトリン を抱きしめた。涙が目に浮かんだ後、彼女は抱擁を返し、さようならを言った。