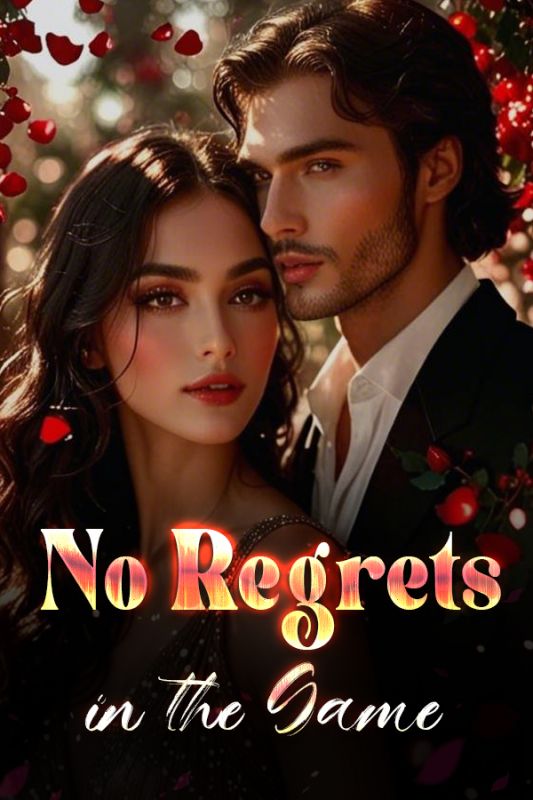あいつと別れてから6年後、俺は人生で一番どん底で、ジョイ・アスターと再会したんだ。
同窓会だった。まさかジョイ・アスターが現れるなんて、誰も思ってなかった。
誰かが冗談っぽく、彼に聞いた。「アスターって、誰とも連絡取らないじゃん。なんで今年、同窓会に来たの?」
「もしかして、クレアが来るって聞いたから? まだクレアのこと考えてんの? クレアを探しに来た?」
隅っこに座ってた俺は、背筋がピンって伸びた。顔を上げると、ジョイ・アスターがタバコをくわえて、俺を冷たい目で見てた。
みんな知ってたんだ。ジョイ・アスターが、どれだけ俺のこと好きだったか。
彼はアスター家の御曹司だったのに、俺に一目惚れしたんだ。
あいつは、俺のために家族と縁を切って、地位も財産も捨てて、必死に俺と一緒になろうとした。
俺たちは、ちっちゃなアパートで、インスタントラーメンを分け合って暮らした。生活は苦しかったけど、すっごく幸せだった。
夜になると、指を絡ませて、永遠に一緒にいようって誓った。
でも、その後、俺は妊娠した。
彼の母親は、俺に300万ドル渡して、子供を堕ろして、彼から離れろって言ったんだ。
あの日、ジョイ・アスターは手術室の外でひざまずいて、ドアを叩きまくってた。
涙を流しながら、何度も俺に懇願した。「ダーリン、ダーリン…俺、頑張って働くから、お金稼ぐから、俺たちが支えるから。何百万も稼いで、全部お前に使わせるから、いいだろ?」
「お願いだから、俺から離れないで、俺たちの子供を諦めないで…」
俺は手術台に寝て、唇を噛み締めて、泣くのを我慢した。
薄いドアを隔てて、ジョイ・アスターが「一生、お前を恨む」って言ってるのが聞こえた。
ジョイ・アスターとの別れが、どれだけ酷かったか、誰も知らなかった。
誰かが俺を彼の方に押しやって、笑いながらジョイ・アスターに聞いた。「ジョイは、昔、クレアのために死ぬほど好きだったんだろ。どうして手放せたんだ?」
みんなが俺たちを煽って、昔みたいにやり直せって言ってきた。
ジョイの友人は俺を見て、ニヤリと笑って、突然口を開いた。「アスターは、どんな女でも手に入れられるんだ。クレアなんて、何なんだよ? なんであいつのために未練がましくしてるんだ?」
彼は、ジョイと3年間付き合ってる女がいるって言った。
その女は、もっと優しくて、可愛くて、俺よりもジョイの彼女にふさわしいって。
ジョイ・アスターは、その女と3年間も一緒にいた。友達はみんな、彼女のことを「義理の姉さん」って呼んでた。結婚するって噂もあった。
笑い声も、おしゃべりも止まった。ジョイの友人だけが話し続けて、みんなをジョイ・アスターの結婚式に誘ってた。
彼は、招待状を俺の方に弾いた。それが俺の顔に当たって、膝の上に落ちた。
俺は下を見た。招待状には、ジョイ・アスターの名前が書いてあった。その隣には、別の女の子の名前が。
彼女の名前はビビアン。聞いただけでも、いい子だってわかる。
俺よりずっとしっかりしてて、素直で、人の世話も上手で、ジョイ・アスターを悲しませたりしないんだろうなって思った。
6年ぶりの再会…ジョイ・アスターが元気でやってるってわかっただけで、十分だった。
落ちてきそうな涙を飲み込んで、顔を上げて、ジョイ・アスターに言った。「おめでとう」
ジョイ・アスターは、俺をじっと見てた。俺の「おめでとう」を聞いて、突然笑った。タバコを乱暴に潰して、冷たく言った。「クレア、結婚式には来ないでくれ」
「俺の奥さんは、お前を見るのは嫌なんだ。彼女が不機嫌になるのは、俺も嫌なんだ」
薄い赤い招待状を握りしめて、俺は一瞬固まった。
それから、笑って、頷いて、小声で言った。「わかった」
あの日、みんなが言ってた。ジョイ・アスターは、もう俺のこと、全然好きじゃないんだって。
俺たちが、どれだけ深く愛し合ってたか、誰も想像できなかった。
結局、彼は結婚することになって、花嫁は俺じゃなかった。
みんな、ジョイ・アスターは、ずっと俺を待ってると思ってた。
みんな、このビビアンって子に興味津々だった。一体どんな子なんだろうって。ジョイ・アスターをこんなに夢中にさせて、こんなに大切にされてるんだから。
ジョイが俺に会いたくないってわかってたから、俺は同窓会を早く出た。
家に帰る途中、友達がビビアンの写真送ってくれた。
写真の彼女は、純粋で無垢な顔をしてた。笑うのが好きで、可愛く甘えるのも上手だって聞いた。まさにジョイが好きなタイプの女の子。
友達が聞いた。「クレア、ビビアンの笑顔って、クレアに似てると思わない?」「ジョイ・アスターは、まだクレアのこと好きなのかな? 本当に終わっちゃったの?」
俺は、小さくため息をついた。長い沈黙の後、笑って言った。「もう、どうでもいい。気にしてない」
もう、ジョイと関わりたくなかった。
俺は、誰にも秘密にしてたことを、彼には知られたくないと思ってた。俺は、こっそり、俺たちの子供を産んでたんだ。
その子は病気だった。死にかけてた。
今年は、俺にとって一番辛くて、一番貧しい年だった。
子供のために、最高の薬を買ってあげたくて、病気の時の痛みを和らげてあげたくて、必死に働いた。
お金のために、プライドを捨てて、同窓会に行って借りたり、クラブでホステスとして働いたり、胃が痛くなるまでお酒を飲んだりした。
あの同窓会が、ジョイと会う最後の機会になるかもしれないって思ってた。
それから数日後、ビビアンって名前の女の子が、俺を見つけ出した。
ビビアンは、他の人から、自分が俺に似てるって言われてるのを聞いて、確かめたかったんだろう。
彼女は、友達とクラブに来て、わざわざ俺を指名した。
ある女の子が、高圧的に言った。「あなたがクレア? アスターの最初の恋人?」
彼女の目は、俺の濃い化粧を見て、軽蔑の色を浮かべてた。まるで、俺が汚いものだって言ってるみたいに。
俺は、拳を握りしめて、怒りを飲み込んだ。面倒なことにはなりたくなかった。「何か飲みますか?」って聞いた。
飲まないなら、俺の時間を無駄にしないで欲しかった。
その女の子は、俺が彼女を軽蔑したと思ったのか、キレた。「何様のつもり? 聞こえてないの? 話してるんだよ! 調子に乗るな」
彼女は、強いお酒のボトルを指差した。「いいわ、クレア、お金が好きでしょ? このボトル全部飲み干したら、20万円あげる」
あのボトルを飲んだら、多分、病院送りになるだろう。
ビビアンは、心配そうなふりをして、その女の子の腕を引っ張った。「私たち、ただ見に来ただけなんだから。クレアに意地悪するつもりはなかったの!」
「みんな、彼女は男を誘うのが上手だって言ってて、気をつけろって言われたんだけど…ジョイも、私が純粋すぎるから、いじめられるかもしれないって心配してたの」
「でも、大丈夫」
ビビアンの話を静かに聞いて、俺はわかった。彼女は、ジョイがどれだけ彼女を好きで、俺のことをどれだけ嫌ってるか、教えてるんだ。
俺は、かすかに笑って、反論せずに、彼女の友達を見て聞いた。「じゃあ、そういうことでいいの? 俺がボトルを飲んで、あなたが20万円くれるってことで、いいんだよね?」
それから、テーブルからボトルを取って、飲み始めた。
みんな、唖然としてた。誰も、俺がそんなにお金のために命をかけるとは思ってなかったんだ。
ビビアンは、俺の手を掴んで、優しく非難するような声で言った。「クレア、どうしてそんなにお金のために自分を貶めるの?」「私たち女は、恥を知らないと。言いたくなかったし、あなたを傷つけたくなかったけど…ジョイが一番嫌いなのは、あなたみたいな女なのよ…」
俺は、胃が焼けるような痛みを感じながら、ボトルを飲み干して、彼女を遮った。「お金は?」「ジョイが何を好きで、何を嫌いかなんて、私には関係ない。ただ、あなたが約束した20万円が欲しいだけ」
ビビアンは、不満そうに眉をひそめて、俺を失望したように見て言った。「クレア、正直言って、20万円なんて、私にとってはポケットマネーみたいなものよ。誰にでもあげられるわ。でも、あなたにはあげられない」「あなたに嫌われてもいいけど、これはあなたの為なの。これ以上落ちていくのを見ているのは耐えられないの…」
彼女の友達が、俺を突き飛ばして、笑った。「冗談だよ。1円もあげないわ。どうするの?」
俺も冷たく笑った。それから、手を上げて、空になったボトルをテーブルに叩きつけた。ガラスの破片が飛び散って、そのうちの一つがビビアンの足に当たって、切り裂かれた。血が溢れ出した。
ビビアンの涙が、すぐにこぼれ落ちた。騒がしかった女たちは、静かになった。
次の瞬間、個室のドアが開いた。ジョイ・アスターが、入り口に立っていて、俺を見た瞬間、動きが止まった。
俺は、硬直して、彼の目を見ることができなかった。
彼は俺を見た。分厚い化粧をして、お金のために男と笑って、媚びてる俺を。一番見られたくない姿の俺を。
他の人に見下されるのは、別に構わなかった。ジョイだけは。ジョイに、俺の人生がこんなに惨めだって知られたくなかった。
でも、結局、その小さな願いも打ち砕かれた。
俺は、残りの力を振り絞って、無表情を作って、顔を上げた。ジョイが手を伸ばして、ビビアンを抱きしめて、優しく彼女の涙を拭うのを見た。
それから、一言一言、ゆっくりと俺に尋ねた。「クレア。俺の前で、誰をいじめてるつもりなんだ?」「金が欲しいのか? いいだろう。まず謝れ」
ジョイがビビアンを守ってるのを見て、俺は昔のことを思い出した。彼は、昔、俺をこんな風に守ってくれたんだ。