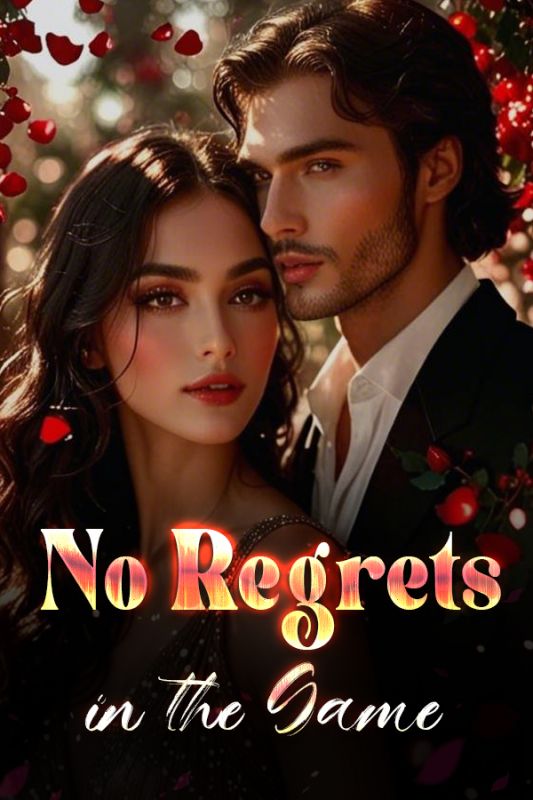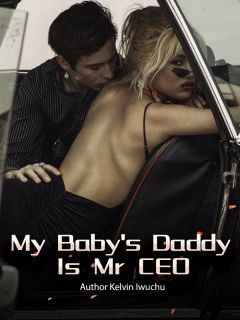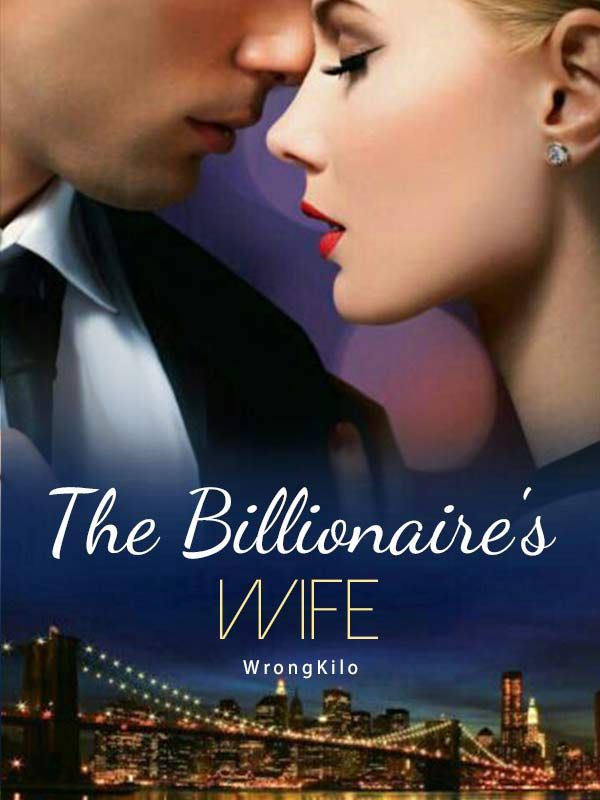「なんで病気なのお前じゃないの」
「なんで死ぬの、お前じゃないの」
男は、一番傷つく言葉を、一番優しい声で彼女の耳元で囁いた。
でも、彼は彼女が本当に死にかけていることなんて、知らなかったんだ。
ソフィアはお腹をぎゅっと掴んで、ベッドから這い出ようと頑張った。
窓から月光が差し込んで、女の青白い顔をさらに際立たせる。
ドアの外から聞こえてくる聞き覚えのある足音──それはジョンのものだった。
ソフィアはどこからか力を振り絞って、ドアノブを掴んでドアを開けた。
「ジョン」彼の名前を呼ぶだけで、ほとんどエネルギーを使い果たしてしまう。
ジョンは足を止めて、振り返って、薄着の女を冷たい視線で見た。
「お帰り。ご飯食べた?」媚びるような口調で、彼女はそう言った。
その美しい瞳には、一筋の光が灯っていた。
ジョンは相変わらず冷たく、遠い表情のまま、立ち去ろうとした。
そんな彼を見て、ソフィアの心はまるで刺されたように感じた。
ソフィアは彼を追いかけ、彼の袖を掴んだ。唇は噛み締めて血が出ていたし、お腹の激痛で呼吸も苦しい。
「放せ!」ジョンは怒りで目を燃やした。
ソフィアは掴む力を弱め、彼のシャツの端っこだけを掴むのが精一杯だった。
「ジョン、痛い…」彼女の声は震えた。「もう遅いから。病院に連れて行ってくれる?」
もしこれが昼間なら、彼に頼んだりしなかっただろうに。
「どこが痛いんだ?」ジョンは振り返って、彼女をじっと見つめた。
「お腹」彼女の額には汗が滲んでいる。
ジョンは彼女がお腹を覆う手を見て、突然嘲笑した。「ソフィアさん、あなたの演技は日に日にリアルになっていくね。これ、どれくらい練習したの?」
彼は手を上げて、彼女の掴んでいる袖を振り払った。
彼は彼女の顎を掴んだ。「お前が俺を裏切ったあの日から、ジョンは一生お前を許さないと誓ったんだ。ただし…」
ジョンは残酷な笑顔を見せた。「お前が死ぬまではな」
その瞬間、ソフィアの血は凍り付いたように感じた。震えが止まらず、ジョンは二度と彼女を見ることなく、寝室に入ってドアを閉めた。
まるでナイフが彼女のお腹の中でねじれているようで、ソフィアは苦しみに耐えかねて体を折り曲げた。
彼女は震える手で携帯電話を取り出し、119番に電話した。
救急車のサイレンが遠ざかっていく音を聞きながら、ジョンの表情は冷たいままだった。ソフィアは自分の目的を達成するためなら、手段を選ばない女だ。
これは、トーマス家が倒産寸前だから、ジョーンズ家に居座るための、いつもの彼女の策略に過ぎない。
誰かが困れば、すぐに見捨てるような女だから、苦しい人生なんて耐えられないんだろう。
…
ソフィアは病院のベンチに座り、検査結果を手に、白い壁をぼんやりと見つめていた。
結果が出た──彼女は進行性の大腸がんだった。
ソフィアはタクシーでミアのいる病院へ向かった。ミアは彼女からの電話を受けて、病院の入り口で彼女に会った。
ソフィアの目は赤く、彼に微笑みかけた。
「ミア」彼女は検査結果を握りしめた。「結果が出たの。医者が言うには、進行性の大腸がんらしい」
ミアの顔色が変わった。
鼻の奥がツンとして、彼女は懇願するような目でミアを見た。「もう一度検査してくれない?もしかしたら…間違ってるかもしれない?」
ミアは医者で、消化器内科の専門医だった。
ソフィアは検査室に運ばれた。
午後5時、結果が出て、最初の診断が確認された。
進行性大腸がん。
ソフィアは呆然とそこに座り、唇を震わせた。「あとどれくらい?」
ミアはしゃがみこみ、骨ばった指で彼女の肩を叩いた。「ソフィア、私が助けてあげる」
「がん」ソフィアの涙がこぼれた。「がんよ」
彼女の病気は、ジョンとの結婚と同じように、治る見込みがないものだった。
部屋は薄暗く、ソフィアは電気もつけずにソファに座っていた。
真夜中、車のヘッドライトが闇とガラスを突き抜け、室内を照らした。
すぐにドアが開き、ジョンが入ってきた。
彼は電気をつけようと手を伸ばし、ソフィアがそこに黙って座っていることにすぐに気づいた。
彼は視線をそらし、ネクタイを緩めながら、二階へ行こうとした。
「ジョン」彼女はそう呼んだ。
彼は足を止めなかった。
ソフィアの指は強く握られ、爪が手のひらに食い込んだ。長い沈黙の後、彼女は顔を上げ、彼の背中を笑顔で見つめた。
「離婚しましょう」
彼女の願い通り、ジョンはついに立ち止まり、振り返った。光に照らされた彼の姿は、いっそう冷たく見えた。
ソフィアの視線は彼の顔をなぞった。これは彼女が10年間愛した男だった。10年間の愛は、彼の嫌悪感を生み出し、彼女は心を痛めた。
もうこれ以上、彼を困らせるべきではない。
「お前は、一日たりとも騒ぎを起こさずにいられないのか?」
彼女はただ、駆け引きをしているだけなのだ。
ソフィアは立ち上がり、バッグから離婚協議書を取り出した。彼女の手は、中に入っている鎮痛剤に触れ、一瞬彼女の目は見開かれた。
それから彼女は静かにバッグを閉じ、脇に置いた。
彼女はジョンのところへ行き、離婚協議書を彼に手渡した。
そこにはすでに彼女の名前がサインされていた。
彼女は自分の感情を隠そうとした。「エミリーと結婚したいんでしょ?」
彼女は笑顔を作った。「私が叶えてあげる」
もし彼がエミリーを好きだと知っていたら、彼女は彼と結婚することはなかっただろう。
二人の結婚は、彼女の一方的なもので、強制されたものだったのだ。
ジョンは彼女のサインを見て、離婚協議書を受け取った。
彼は頬の内側を舌で押し、その紙を彼女の肩に叩きつけた。
「ソフィアさん、さすが金融出身」彼は近づき、冷たい目で言った。「この離婚で、ジョーンズ家の財産のどれだけを、持っていくつもりですか?」
ソフィアは一瞬驚いた。彼女は唇を固く結び、小声で言った。「あなたの金なんて、欲しくないわ」
ジョンは何も言わず、ただ冷たく彼女を見つめていた。
3年前、ジョンのお父さんが投獄され、借金を返済するために彼のすべての事業が売却され、ジョーンズ家は危機に瀕した。
その時、彼は無一文で、彼を愛していると主張していたこの女は、彼の苦難の翌日には姿を消したのだ。
後になって、彼女がウィリアムと一緒にいるところをあちこちで見かけたと聞いた。
ブラウン家は、彼のお父さんを投獄するように仕組んだ連中だった。
彼のお父さんはソフィアにとても優しかったのに。
でも彼女は、金のために自分を売るような女だった。彼女にできないことなど、何もないだろう。
そして、ソフィアは、彼女のお父さんに何を言ったのか、彼に無理やり結婚させられたのだ。
「出て行け」彼の目は冷たさに満ちていた。
彼は立ち去ろうとしたが、ソフィアは両腕を伸ばして、彼の行く手を遮った。
「エミリーが好きでしょ?私が叶えてあげる。宣誓供述書にサインするわ。あなたからは一銭ももらわない!」
「ああ、エミリーが好きだ」ジョンはそう言うと、目を細め、唇を笑顔にした。「だから、彼女を妻にするために盛大に登場するんだ」
彼は目を細めた。「お前と絡んでいる間はな」
ジョンの入ったバスルームに、ドアがバタンと閉まる音が響いた。冷たい水が流れ落ち、彼は唇を噛み締め、拳を握りしめた。
ソフィアは振り返り、床から離婚協議書を拾い上げた。
電話が鳴り、お母さんが泣きながら電話口に出た。
彼女のお父さんは重い病気で入院していた。
ソフィアは急いで行き、お母さんから、トーマス家が倒産寸前で、お父さんが重い病気になっていると聞いた。
突然、彼女はジョンの言葉を思い出した。
彼から離婚して、ジョーンズ家の財産をどれだけ持っていくのか。
なるほど、彼はそう言ったんだ。彼は、トーマス家が倒産寸前だと知っていたに違いないのだ。
ジェニファーはソフィアの細い腕を掴んだ。「ソフィア、ジョンに頼んで。あなたは彼の奥さんなんだから。断らないはずよ」
「彼は私をすごく嫌ってるの」ソフィアはそう言うと、暗い笑顔を浮かべた。「どうして私にお金をくれるの?」
ジェニファーはソフィアの頬を叩いた。「お父さんの死を見たいの?あなた、何にもできないのね!」
ソフィアの唇は震え、彼女は母親を冷たい目で見た。
ジョーンズ家が困った時、ウィリアムは彼女に近づき、母親の不倫の証拠を持っていると言った。彼はまた、もし彼女がジョンを捨てれば、ジョンの借金を返済するために大金を提供すると言ったのだ。
彼女はジョンの父の問題に、ジョンがどうしようもなく苦しんでいるのを見ていた。
彼女にできることは、心配することだけだった。
その時、彼女はジョンを助けることができれば、彼に誤解されても構わないと思ったのだ。
彼女はウィリアムから金を受け取り、ジョーンズ家の資金不足を補うために使った。
彼女は辛辣な言葉を言い、ジョンを傷つけた。
二度とジョンと会うことはないと思っていたのに。
ある日、ジョンの父が彼女に話しかけてきた。病院のベッドの男は、呼吸することさえ苦しんでいた。
彼は彼女にジョンと結婚してほしいと願った。彼は、彼女の置かれた状況を理解していると言った。
その翌日、彼女の家族はジョーンズ家から大金を受け取った。
彼の父に結婚を強要され、ジョンは彼女を心から憎んでいた。
ソフィアは病室から出て、鎮痛剤を飲み込んだ。
彼女が去ろうと足を上げたとき、病院のガウンを着た女が横に立っているのに気づいた。
その女はとても白い肌をしていて、丸くて大きな目、繊細な鼻と口をしていた。
彼女の名前はエミリー、ジョンが今愛している女、そしてかつての親友だった。
ソフィアは視線をそらし、去ろうとした。
「ソフィア」エミリーが彼女に声をかけた。
ソフィアは歯を食いしばり、歩き続けた。
彼女の後ろから、女の笑い声が聞こえてきた。「トーマス家が倒産寸前だって聞いたわ」
彼女はソフィアに追いつき、彼女の目の前に立って、冷たく言った。「因果応報よ」
ソフィアは冷たく彼女を見つめ、「消えろ」と言った。
エミリーは動揺せず、何気なく自分の爪をいじりながら言った。「ジョンがもうあなたを欲しがっていないのに、あなたにしがみついているなんて、本当にみっともないわね」
彼女の目は勝利に輝いていた。「知ってた?ジョンはここ数日、私のそばにいるのよ」
「あなたがジョーンズ夫人の座を狙ってるんでしょ?」ソフィアは唇を引き締めた。「彼に離婚について話に来るように言って」
エミリーは目を細めた。「彼があなたを忘れられないから、離婚しないと思ってるの?」
エミリーは笑い出した。「ソフィア、あなたは本当にナイーブね」
彼女はソフィアに近づき、「彼はただ、あなたに同じ気持ちを味わわせようとしているだけなのよ」
「彼に飽きられたら、あなたはゴミと変わらないわ」エミリーは彼女の耳元で囁いた。「そうね、彼はあなたに一度も触れてないんでしょ?」
ソフィアの指は強く握られた。彼女は頭を下げ、冷たい視線でエミリーを見た。
「なぜだと思う?」エミリーの爪はゆっくりとソフィアの頬をなぞった。「だって、彼はあなたが汚いと思ってるからよ。ジョーンズ家の借金を返済するのに使ったお金は、実は、あなたがジョンに渡した別れ金、そしてあなたの愛人ウィリアムがくれたものだって聞いたわ」