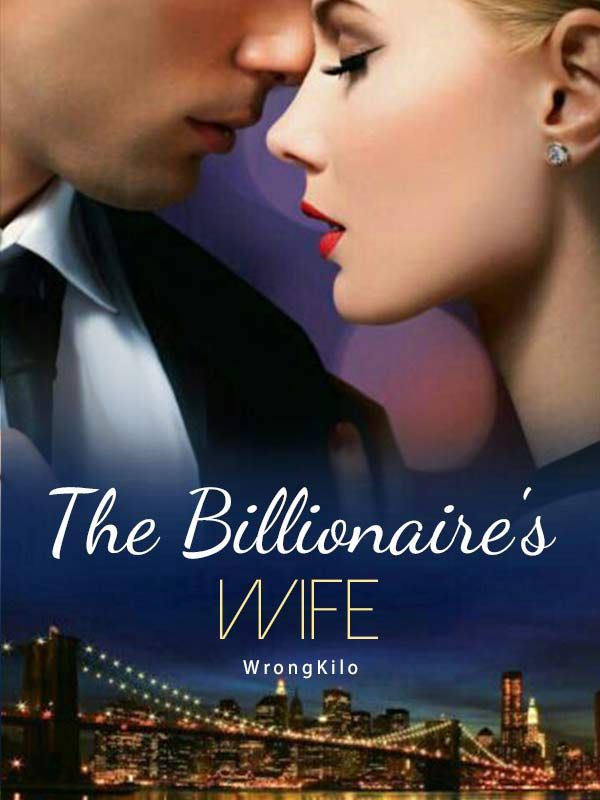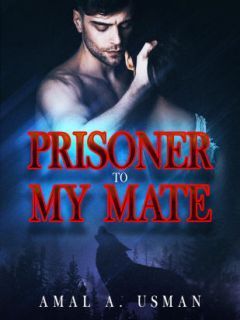毎晩、**ライアン・ジョンソン**は違う女の子を連れて帰ってきて、あたしは彼の代わりの恋人だった。あたしは3人分の晩ご飯を作って、彼が帰ってくるように電気をつけっぱなしにして、他の女の子の香水の匂いまで拭いてあげたんだ。彼の友達はみんな、彼は何でも許せる完璧な代わりを見つけたって言ってたけど。でも、あたしには理由があったんだ。
3年前、あたしが心の底から愛していた**ネイサン・ミラー**は、交通事故で死んだんだ。
それから、あたしの人生のすべてが意味を失ったように感じた。でも、代わりっていう役割だけは、あたしに生きる理由をくれた。
**ライアン**は金持ちの御曹司で、前の彼女のことをすごく愛してた。
あたしは一度、彼の前の彼女の写真を見たことがある。彼女はまるで天使みたいで、比べものにならないくらい魅力的だった。**ライアン**はあたしを初めて見たときから追いかけてきたんだ。だって、あたしは彼の前の彼女に6割くらい似てたから。あたしは**ライアン**の代わりの恋人になった最初の人間じゃないし、最後の人間でもない。でも、一番長く彼のそばにいたのはあたしだった。だって、あたしは気が利くし、彼のことをよく我慢できたから。あたしは性格も良かったし。朝4時に彼の友達からの電話に出て、彼を迎えにナイトクラブに行ったこともあった。たとえ彼が他の女の子の首に腕を回されていても、あたしはしゃがんで、彼の顔を濡れたティッシュで丁寧に、少しずつ拭いてあげることができたんだ。あたしは他の女の子の腰から彼の腕を外して、彼の指、手のひら、手の甲を濡れたティッシュで優しく拭いた。**ライアン**の指が少し動いて、すぐにあたしの顎をつまんだ。いつから目を開けていたのかわからなかった。彼の黒い瞳は、酔っ払ているのか少し赤くなっていて、それが彼の視線をさらに魅力的にしていた。「いつ来たんだ?」**ライアン**が聞いてきた。
「たった今」あたしは笑顔で答えた。**ライアン**は動かず、あたしを見下ろしていた。
彼はあたしをじっと見つめて、何かを尋ねるような表情をしていた。
「**シャーロット・グリーン**、なんでお前は怒らないんだ?」**ライアン**が聞いてきた。
あたしはもう片方の手で、丁寧に、ゆっくりと拭き続けた。
「怒ることに意味があるの?」あたしは問いかけた。「じゃあ、あたしが怒ったら、あなたは他の女の子とデートするのをやめるの?」
**ライアン**は笑った。少し酔ったような目で、唇の端をわずかに上げた。
「ごめん、それは無理だな」彼は答えた。**ライアン**は、まるで人が変わったように、楽しそうに、いたずらっぽく笑った。
しばらく笑った後、彼は突然手を伸ばして、あたしが結んでいた髪の毛をほどいた。あたしはメイクもコンタクトレンズもつけないで飛び出してきたから、急いで黒縁メガネを手にとったんだ。
髪をぐちゃぐちゃにした後、彼はあたしのメガネも取った。
彼はソファーに寄りかかって、あたしを上から下まで見ていた。
「ああ、それだよ」彼は満足そうに頷いた。**ライアン**は、あたしが髪を結んだり染めたりするのが嫌いだったし、メガネをかけるのはもっと嫌いだったんだ。
一度、あたしは彼に医者に行ったほうがいいんじゃないかって聞いたことがある。彼は後ろからあたしを抱きしめて、あたしの耳たぶをくすぐって、それがむずがゆかったんだ。
「もう医者には行ったんだ。ただの病気なんだよ」彼は答えて、狂ったように笑った。「治りたくもないんだ」
「**シャーロット**、お前はどんな男が好きなんだ?」それから彼はあたしにキスをしながら聞いてきた。
あたしは指を伸ばして、彼の眉と目に沿って滑らせた。目を閉じて、彼の喉仏にキスをした。
「あなたのままで好きだよ」あたしは優しく答えた。
彼の喉仏が小さく動き、彼の目が暗くなった。
「お前は嘘がうまいな」彼は言った。
でも、これらの行動すべては、**ライアン**が新しい人を見つけるのを止めることはなかったんだ。
あたしが料理をしているときに、彼が初めて女の子を家に連れてきたとき、その女の子は入ってきたあたしを見て明らかに驚いていた。あたしの表情にもかかわらず、彼は冷静だった。「我慢できないなら」彼は冷笑して言った。「出て行けばいい」あたしは彼らの親密さを見ていた。
**ライアン**の手がその女の子の腰にあるのを見て、あたしの心の隙間に、突然ひとつかみの塩が振りかけられたように感じた。
あたしは目を伏せて、ゆっくりとダイニングチェアを開き、リラックスしたふりをしてみた。
「**おばさん**が今日、新鮮な渡り蟹をたくさん買ったんだ。まず食べよう」あたしは優しく提案した。
その女の子は明らかに困惑していた。
「大丈夫だよ、一緒に食べよう」あたしは女の子に笑顔で言った。
でも、その女の子は、部屋の奇妙な状況に明らかに戸惑っていた。二口食べた後、彼女は言い訳をして出て行ったんだ。
「ちっ、興ざめだな」**ライアン**は不満を言い、自分のボウルも押しのけて食べるのをやめた。
あたしは、彼が誰に話しかけているのかわかっていた。
あたしは彼のスープをもう一杯注いだ。
「ごめんね、今度誰か連れてきたいときは、部屋を空けておくわ」あたしは言った。**ライアン**は椅子にしゃがみこみ、片手で顎を支えてあたしをじっと見つめていた。まるであたしの心を見透かしているかのようだった。
彼は笑い、あたしを挑発しようと、露骨な言葉でからかった。
あたしは彼の視線を避け、ボウルに長く入っていて冷たくなったご飯をいじっていた。一口食べようとしたら、むせてしまって、目がうるうるしてきた。
「あなたが何人のガールフレンドを連れて来ようが、家に連れて来ようが、あたしは気にしない」あたしは彼を見上げて言った。「ただ、あたしを突き放さないでほしい。ここに一緒にいたいんだ」
**ライアン**は黙り込み、彼の笑い声は消え去った。彼は立ち上がり、あたしを見下ろした。
「わかった、我慢できるなら」彼は言った。次から次へと、**ライアン**の周りの女の子は変わっていったけど、それは彼の人気には影響しなかった。
**ライアン**は金持ちの家柄で、御曹司だった。女の子と別れた後、彼は彼女に大金、家、車をプレゼントしたんだ。
だから、彼が不誠実でも、別れた後に彼にしがみつく女の子はいなかった。でも、あたしは例外だった。あたしは彼にとって本当に厄介な存在だったみたい。
あたしと付き合って2ヶ月後、彼は飽きて別れたがった。
「車か家か、どっちか選べ」**ライアン**は、ランボルギーニの車の鍵をテーブルに投げつけた。「どっちも気に入らないなら、200万ドルを口座に振り込むよ」
あたしは首を横に振って、彼の車のかぎを彼に返した。それから、彼がくれたバッグを返し、立ち去ったんだ。
あたしが振り返った後、彼のことじゃなく、涙が止まらなかった。
3日後、**ライアン**は泥酔して身なりも気にせず、あたしの家のドアを叩いたんだ。