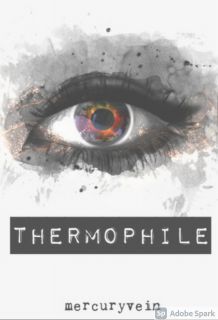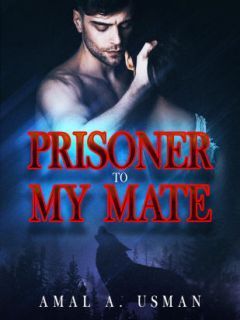
紹介
目次
紹介
アナは、そこにいるすべての若いメスオオカミのようでした。
彼女は自分のメイトに会うのが待ちきれませんでした。
彼女は、ついに彼に会った日や、彼らに会った後の彼の彼女への接し方がどうなるか予想していませんでした。
アナのメイトは彼女と何の関係も持ちたがらないが、彼女を手放そうとはしません。アナは自分のメイトの囚人のように感じています。
彼女の心は、何をすべきかで引き裂かれています。彼女は自分のメイトが彼女を愛してくれることを願っていますが、彼はその希望を示しません。
彼女は彼と何かを築こうとしますが、彼は彼女を困難にします。彼は彼女をひどく扱い、アナは理由がわかりません。
アナは彼が拒絶するか、彼女を手放してくれることを願っていますが、彼はそうしません。彼女は、彼が永遠に彼女を自分の囚人にしようと決めているように感じています。
アナがどのようにして自分の囚人として生き残るのかを読んでください。
もっと読む
すべての章
目次
第一章
第二章
第三章
第四章
第五章
第六章
第七章
第八章
第九章
第十章
第十一章
第十二章
第十三章
第十四章
第十五章
第十六章
第十七章
第十八章
第十九章
第二十章
チャプター21
チャプター22
チャプター23
チャプター24
チャプター25
チャプター26
チャプター27
チャプター28
チャプター29
チャプター30
チャプター31
チャプター32
チャプター33
チャプター34
チャプター35
チャプター36
チャプター37
チャプター38
チャプター39
チャプター40
チャプター41
チャプター42
チャプター43
チャプター44
チャプター45
チャプター46
チャプター47
チャプター48
チャプター49
チャプター50
チャプター51
チャプター52
チャプター53
チャプター54
チャプター55
チャプター56
チャプター57
チャプター58
チャプター59
チャプター60
第61章 エピローグ