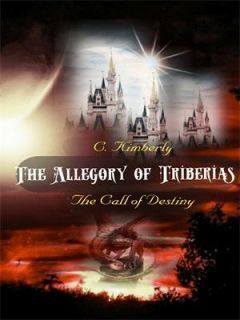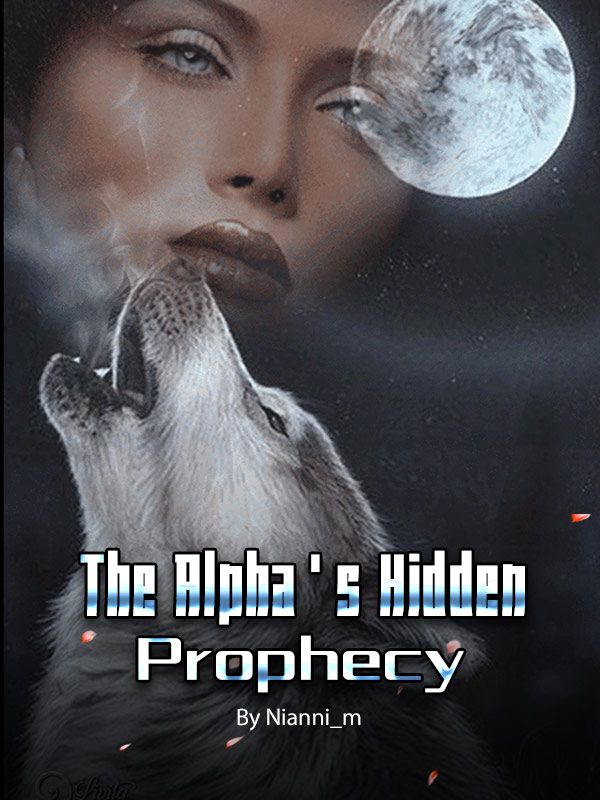エリドリア、
東の大陸
2400 AA(大昇天の後)。
優しい風が大地をなぞる。砂が動き、突風が空っぽのビーチを吹き抜け、大きな崖の後ろにある岩だらけの地形を越えていく。荒野や森を越え、風が漂い、長い草の葉や密集した花のパッチの中で、蛾や蛍を踊らせた。
それは葉を揺らし、サバンナの香りを掻き立てた。花の香り、土の豊かな匂い、暖かい草の匂いが、海と塩の味と混ざり合い、風が過ぎ去った後も長く空中に漂っていた。
半島のすべてが静かだった。ベテスダという小さな港町では、嵐の前の静けさのようだった。
風はさらに強くなり、海の底から灰色の厚い雲の小さな群れを運んできた。かつて真昼に大地を焦がした湿った空気の熱を奪う冷たさが漂い始めた。
また一日が終わろうとしている。
地球が半分だけ回り、そのようにして光は優しい風のように消え去った。一日の喜びとその征服は、夜の到来とともにすぐに忘れ去られることだろう。
どうしようもない。暗い呪いから逃れる方法はない。
これはベテスダの住民がよく知っている事実であり、彼らが急いでいる様子からも明らかだった。商人は、空っぽになる町の広場を後にしながら、商品を急いで詰め込んでいた。誰もが自分の家へ。呪いを出し抜き、新しい日の到来を告げる光を見るために目覚めるというかすかな希望を抱きながら、自分の住処へ。
町の広場のように、波止場も空っぽになった。漁師たちは日没の数時間前に網を引き上げ、今、残っているのは、人を欺くように揺れる係留されたボートだけだった。さざ波の優しさは平和を予言するものではなく、むしろこの時代においては、嵐の前の兆候となる静けさだった。すぐに彼らに降りかかり、朝になって初めて、彼らはそのあらゆる荒廃を語ることができ、それが残した命のすべてを救済することができた。
町の広場はすぐに空っぽになり、残ったのはたくさんの空っぽの小さな小屋と木製の屋台だけだった。窓やドアを閉める音が郊外に響き渡り、強風が唸り続けていた。時間の経過とともに強くなっていった。
一人の女性が走り去るのが見えた。恐怖の表情が顔を歪ませ、しばらくして、彼女は彼女の腕から去ることに落ち着かないように見える叫び声を上げている幼児を抱えて戻ってきた。それでも、女性の態度は以前よりも安心していた。
まだいくつかの
苦痛の兆候があったが、彼女はうまくやったことを嬉しく思っていた。外に捕まったら大変なことになっていただろうが、彼女は夕暮れに勝ったのだ。彼らは今、安全だろう、少なくとも彼女はそう願った。
他の場所では、小さな子羊が鳴いた。それは母親と大きな雄羊を、家の地下室の中に建てられた仮設小屋に追従した。チャンスはなかった。すべてのペットが通りから連れ去られ、すべての動物も閉じ込められた。暗闇は動物と人間の区別をするのか?ノー、そして誰も知りたくなかった。この世界で物事を発見する代償は、しばしば高すぎる。より少ない動物と質素な背景を持つ多くの人々にとって、それは彼らの人生が今のようにある方法で彼らが余裕がない選択肢ではなかった。危険なものは常に軍隊に任されている。したがって、これはベテスダの港町に住むすべての生き物が従うべき厄介事だった。規範は生き残るために中に引っ込むことだった。そして、このように、これはこの世界の呪いだった。星が天でまたたくのを見ることも、広大な空を旅する月を見ることもなく、そうでなければ確実な死を意味するだろう。