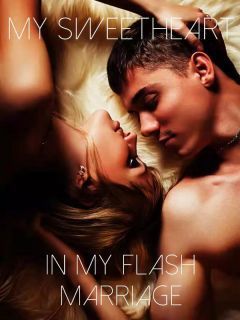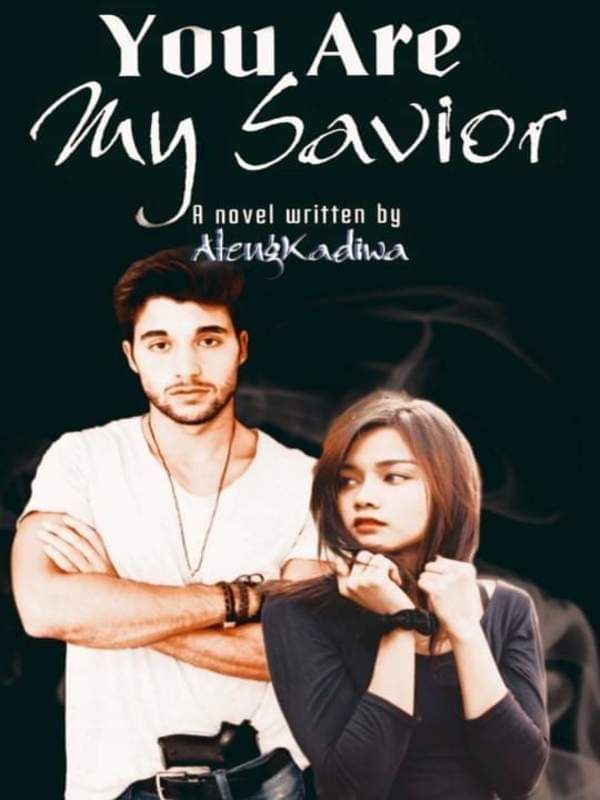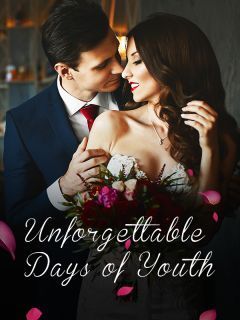『ニュース速報です。3人の人間の死体が血まみれで家の中で見つかりました。死体の胸には「D」という文字が刻まれていました。現場近くの住民によると、家からは物音や叫び声は聞こえなかったそうです。警察は現在、この事件の捜査を開始しています。』
「今のところ、要注意人物がいます。被害者の遺体の詳細を入手し、調査した結果、被害者の胸にある「D」の文字は、この人物の仕業である可能性が高いと考えています。」
私は笑ってテレビを消し、席を立った。家のキッチンに向かって歩き始め、周りを見回した。
「何がいいかな?」と自問自答し、引き出しにナイフが置かれているシンクに近づいた。
ナイフを取り、その切れ味を見た。
「切れ味が悪いな、胸に刺したら痛いだろうな」と言い、ポーチに手を戻した。キッチンをもう一度見回し、引き出しを見た。
すぐにそこに行き、その引き出しを開けた。中に入っていた長いロープを見て驚き、それを取り出して調べた。
「これを使ったら、首を吊る時に痛いだろうな」と言い、ため息をついた。
「何がいいかな?痛くないやつがいいんだけどな」と、手に持ったロープに話しかけた。
ロープを見ながら一人で笑い、引き出しに戻し、リビングに戻った。
ポケットで携帯電話が振動したことに驚き、すぐに取り出すと、誰かから電話がかかってきていた。
「もしもし?」と電話に出た。
「口座から支払いを受け取ってください。もう振り込んであります。ボスが、お前の才能のおかげでボーナスをくれたんだ。ボスもありがとうって言ってるよ。」私は笑って、グラスにワインを注ぎ、座った。
「ボスに伝えてくれ、痛くなく死ぬ方法について何か提案があれば教えてくれ、って」と言うと、相手が笑うのが聞こえた。
電話を切って携帯電話の電源を切り、携帯電話を置こうとしたら、また振動した。ボスからだ。
まずグラスのワインを飲み干し、それから電話に出た。
「他に何かあるのか?」突然、彼の笑い声が聞こえた。
「自殺しようとしてる時に邪魔しちゃったかな?」と彼は尋ねた。
私は笑った。
「まだ方法を考えてるところだよ」と言うと、彼はさらに笑った。
「隠れ家に来てくれ、何か新しいことをやろう」私は頭を掻き、ソファに寄りかかった。
「誰だって教えてくれ」と言った。
「急ぎすぎだよ、まだ様子も見てないのに、来いよ」ため息をつき、立ち上がった。
「わかった」と言って電話を切り、バイクのキーとコートを取り、家を出た。すぐにバイクに乗り込み、隠れ家に向かって運転した。
しかし、隠れ家に着く前に、すぐにバイクを道路の脇に寄せ、その下をダムからの水が勢いよく流れる橋の前に立った。
ポケットからタバコを取り出し、コートの左ポケットからライターを取り出して、唇にタバコをくわえた。橋の下を見て、考えた。
「溺れたら、痛みは一瞬だよな?そうだよな?」と自問自答し、頭に手を置いた。
考えなければ、自分の疑問への答えがわかるはずがない。すぐに橋に登り、欄干に立った。タバコを吸い、煙を吐き出した。
「ついに、安らぎも来る」と言って微笑んだ。目を閉じ、冷たい空気のそよ風を吸い込んだ。
再び目を開き、唇からタバコを取り、橋の下に落とした。水がタバコを揺らしているのが見えた。
「次は僕だ」と言い、ゆっくりと向きを変え、目を閉じた。
「さようなら」とささやき、激流に身を投げようとしたその時、誰かが私を後ろに引っ張り、橋の欄干から引きずり下ろし、私は目を開けた。再び目を閉じると、自分が道路に落ちているのが見えた。
「うっ!」と呻き声を上げ、体が床に倒れた。最初にコンクリートの道路にぶつかった頭を抱えていた。
「大丈夫?」と、話しかけてきた相手を見て、驚きと不機嫌さを感じた。目の前に座っているのは、赤いドレスを着て、茶色の髪を結った白人女性だった。鼻が高く、眉毛が濃く、まつ毛が長く、目は茶色だった。唇はピンク色で、顔の色は赤くなっていた。
「あなたは誰ですか?」と私が尋ねると、彼女は足を止め、じっと私を見つめた。私は瞬きをし、頭を抱えながら席を立った。
「くそ、痛てえな」と私はうめいた。
「本気でそんなこと聞いてるの?」私はもう一度、目の前の女性を見た。
「冗談だと思ってるのか?」私がそう尋ねると、彼女は突然のことに吹き出し、私を見て立ち上がった。
「あなたを助けただけなのに、なんで橋の欄干にいたんですか?死にたかったのか…」
「誰が私を助けろって言ったんだ?」と私がイライラして尋ねると、彼女はさらに衝撃を受け、私を信じられない様子で見た。
「はあ、あなたが私を助けなければ、もっと早く溺死していたかもしれないのに」と苛立ちながら言った。
「あなたは気が狂ってるの?」と彼女は信じられないといった様子で尋ね、私は彼女をもう一度見た。
「私を困らせる」彼女はそう言って背を向けた。
「うわあ、助けてもらったことに感謝するどころか、まるで嫌がらせのように助けられたみたい」と私は彼女が言うのが聞こえた。
「本当に嫌なんです」と私はささやき、バイクに近づき始めた時、頭に何かが当たって痛みを感じたので、立ち止まって頭を抱え、背後の女性の方向に目を向けた。
彼女はしゃがみこみ、小さな石を持っていた。
「何なんだよ!」と私が怒って尋ねた。
「感謝しないの!?」と彼女は怒って尋ねた。
「何に?」と私が尋ねると、彼女は笑って困惑した。
「あなたを助けたからよ!あなたは命の恩人なんだから…」
「じゃあ、ありがとう!」と私が言って、再び背を向けた。
「おい!感謝の気持ちが鼻から出てきたわよ、ちゃんと感謝しなさい!」誰かにまた頭を殴られて金縛りにあった。私は落ち着いて、再び彼女に激しく向き合い、彼女の方向に顔を無表情にして、すぐに彼女に近づき、彼女は足を止め、怖がり始めた。
私はすぐに彼女を近づけて、彼女の目を見た。
「ありがとう」と私は彼女の目を見つめながら素早く言った。
「自殺を邪魔してくれてありがとう」と付け加えると、彼女の目は見開かれ、すぐに私を突き放した。私は衝撃を受け、彼女の反応を見た。
「あ、あなたは自殺しようとしてるんですか?」と彼女は尋ねた。
「当たり前じゃないか?」と私がイライラして尋ねると、彼女は飲み込み、私を異端者として十字を切った。
「神様、彼の罪をお許しください。彼は自分が何をしているのかわかっていません」と彼女はささやいたので、私は立ち止まり、ただ彼女を見て、深呼吸をして、彼女から再背を向けた。
「アーメン」と言って、自分のバイクに近づき、乗り込んだ。
「おい!マン!」まだそこに立っている女性をもう一度見た。
「祈り終わったのか?」と尋ねると、彼女の顔には信じられない表情が浮かんだ。
「本気でそうなんだね!どんな問題を抱えているにせよ、自殺は解決策ではありません。」突然彼女がそう言ったので、私はヘルメットを被り、彼女を真剣に見つめた。
「まだ生きているのはラッキーだよ。多くの人が長生きしたいと思っているのに、あなたは人生を無駄にしようとしているのか?自殺するのではなく、祈りなさい。」彼女がそう言ったので、私はヘルメットを被り続け、彼女を見た。
「わかった、あなたは私を祈ってくれ」と言うと、彼女は驚いた。
「え?」と彼女は尋ね、私はバイクを始動させ、彼女の顔に光を当て、彼女を眩惑させた。
「言っただろ、ただ私を祈ってくれって」と言うと、彼女は私を見た。
「う、わかった、あなたの名前は?」と彼女は混乱しながら尋ねた。
私は笑って、バイクの向きを変えた。
「デイモンだよ」と答えてバイクを始動させた。