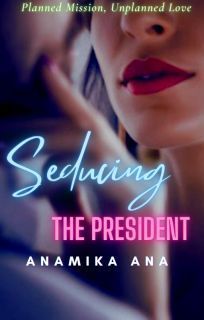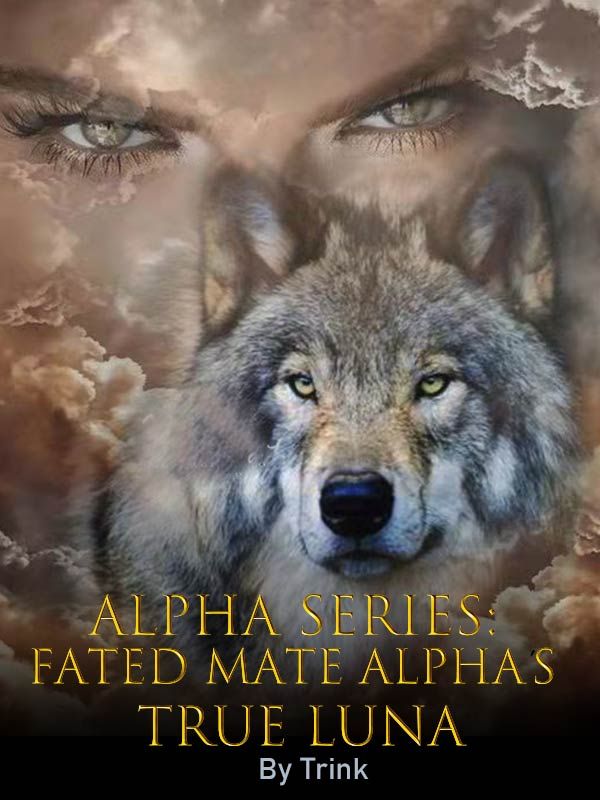紹介
目次
紹介
アダム・ブレイクは、2000年以上後の星間開発時代にタイムスリップし、銀河系の惑星の落ち目の領主となった。彼は海賊システムを起動し、人々を恐怖に陥れる海賊王となった。ある男爵は「何だと!あの狂人が私の領土に来て、また天然素材を略奪したのか!」と叫び、ある子爵は「この野郎!...」と怒鳴った。
もっと読む
すべての章
目次
第1章 黙示録前の再生
第2章 才能に満ちて
第3章 お前は死ぬ
第4章 ツールマン
第5章 夜の悪魔
第6章 部隊
第7章 アーチャー
第8章 空間リング
第9章 夜の影
第10章 死体の群れ
そんなに頼りない
力ずくで売買しようとしてるのか
あなたのために門番
何をしているのか分かっているのか
その笑顔を私に見せ続けて!
力を使って人々を抑圧しても、私を責めないでください。
何、そうは見えない
そんな風に私を見ないで。
ただ私の拳があなたより大きいから!
どういう意味ですか
1億分の1のチャンス
本当に余計なお世話だね
バーメイド
第24章 少しのお金に困らない
第25章 シミュレーション戦闘
第26章 死ねばいいのに
第27章 願いを叶える
第28章 この女のフーリガンはどこから来たのか
第29章 メデューサフリゲート
第30章 私を笑い死にさせようとしているのか
第31章 幸運を祈る
第32章 一体誰だ!
第33章 皆を殺さない理由
第34章 言い訳を見つける