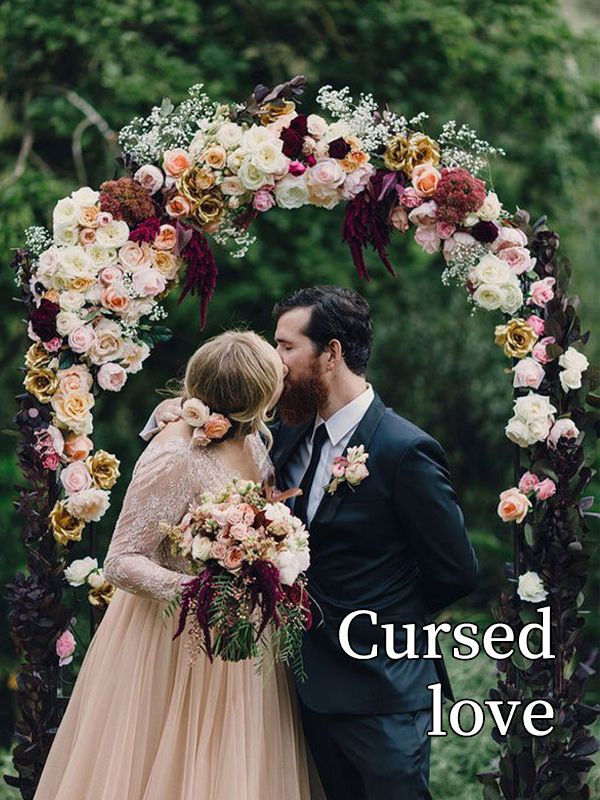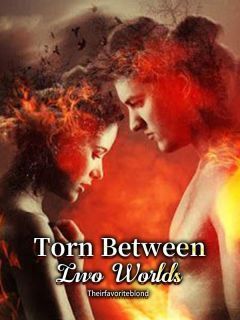宿題のことを考えながら、歌を口ずさみ、カウチにバッグを投げつけ、階段を上がった。大きな笑い声が耳に飛び込んできた。驚いて、閉まった書斎のドアに向かい、顔をしかめた。お客さん? 私はもっと近づき、聞き耳を立てた。別に好奇心があったわけじゃない。おじいちゃんが仕事の話をするのを聞きたいわけでもない。でも、もう一方の声が聞き覚えがあるような気がした。ますます眉間にシワが寄る。「ああ、そうそう、覚えてるよ! 素晴らしいパーティーだったね。ねえ、ジョンソン氏、あの夜は楽しかったでしょう?」 おじいちゃんがからかうような口調で言った。ジョンソン氏! 私たちの街の市長だ! なんでここにいるの? 私はこれに口をあんぐりと開けた。40歳の市長は、私たちにとって有名人のようなものだった。テレビでしか見たことがない。声が聞き覚えがあると思ったのも無理はない。うちの父は彼の熱狂的なファンだったんだ。もう一人の男はくすくす笑った。「ああ、まあ、そうだな、じいさん。お前の言うとおりだ。」
私はもっと近づき、鍵穴から二人の遠い影をじっと見つめた。グランプスはため息をつき、どうしようもないと首を振った。「どうしたんですか、ジョンソン氏?」 おじいちゃんは珍しく真剣な声で言った。それを見て、私は濃い青色のショートスカートを握りしめた。お腹の中で何かが、次の言葉は聞きたくないと告げていた。市長はしばらく沈黙した。鍵穴からは彼のまっすぐな背中しか見えなかった。「もうすぐ、エクリプスが来る。ご存知ですよね? ブラウン氏?」
グランプスがうなずくのが見えた。もしおじいちゃんのことをよく知らなかったら、彼の硬直した体には気づかなかっただろう。でも、私の心は別のところにあった。エクリプスという言葉が頭から離れない。私たちと何の関係があるんだろう? もしかして…。「嫌!」 私は大声で叫び、グランプスが椅子から飛び跳ねるのを見た。市長まで振り返って、驚いた顔をしている。しまった! 私は心の中で悪態をつき、ドアを開けて、他の人たちに姿を現した。「あ、あ、市長…」 私はためらいがちに彼に近づいた。「エクリプスという言葉を聞きました。まさか…?」
涙で視界がぼやけて、次の言葉を口にすることさえできなかった。何度も瞬きし、歯を食いしばった。感情をコントロールして、エミリー! 市長は私を見て、同情の表情を浮かべていた。彼はゆっくりとグランプスの方を向いた。「今年は、エミリーとルーシーだ。私は…」 彼でさえ、何を言えばいいのかわからなかった。でも、私は彼に集中する気分じゃなかった。最後の言葉で、私は部屋の真ん中で凍りついた。その時、自分が何を感じているのかわからなかった。もしかしたら、喪失感? 不幸? 悲しみ? 恐怖? それとも、全部が一緒になっているのだろうか。でも、顔には出せなかった。何度も瞬きし、涙をこらえようとした。市長が何を言っているのかはわかっていた。私たちの現代世界は、太陽とテクノロジーで満たされているはずなのに、闇の影が差している。ヴァンパイアだ。彼らは1、2世紀前に人間に問題を起こした。その時、市長は歯を食いしばって、ある取引をした。両者はこう書かれた書類に署名した。
「私、ロサンゼルスの市長は、エクリプスごとに若い女の子を寄付としてヴァンパイアの王に差し出すことを約束します。私たちに必要なのは、お互いの間の平和です。お互いに迷惑をかけずに、幸せに暮らせますように。市長。」
これは、学校に入って最初に教えられたことだから知っている。未来に備えるためだった。でも、私はそうじゃなかった。世界を救うためだけに、一生ヴァンパイアに仕えることに誰が備えられるだろうか? これは私にとって大きな責任だった! 必死にこらえようとしていた涙が、目からあふれ出し、頬を伝った。チクチクするけど、私の手は言うことを聞かない。疲れと落ち込みを感じた。「エミリー?」 しわがれた声が聞こえ、私はグランプスの悲しい顔を見た。彼の恐怖に満ちた青ざめた顔を見た途端、私は凍りついた。どうして、彼の気持ちを考えなかったんだろう? 彼のたった二人の孫娘が差し出されることになる。彼はもう老人だ。私の涙を見て、心臓発作を起こしてしまうんじゃないだろうか? 私は震える息を吸い込み、涙を拭った。無理やり笑顔を作り、彼を見た。「グランプス、大丈夫だよ。みんな、こうなるってわかってたんだから。」 唇が震えながら、私はそう小さくつぶやいた。返事を待たずに、私は踵を返し、部屋から逃げ出した。足を引きずりながら階段を上がり、自分の部屋の鍵を開けて、後ろで閉めた。倒れ込み、膝の間に頭を抱え、涙が止まらない。私のすすり泣きが部屋に響き渡った。悲しくないわけがない。私は自分の気持ちをグランプスに嘘をついたんだ。彼を置いて行きたくない。まだ。仕事をして、グランプスと妹と数年過ごして、結婚して、子供が欲しかった。母がそうしていたように、学校の門で子供たちを待ちたかった。有名なジャーナリストになりたかった! どうしてこんなことが私に起こるんだろう? 私が選ばれたら、誰がグランプスの面倒を見るんだろう? エクリプスのたびに、街から何人かの女の子が選ばれて、ヴァンパイアのパーティーに参加し、そのうちの何人かがヴァンパイアに寄付される。私は妹の友達が何人も行くのを見てきた。妹が友達の一人がパーティーに行って二度と帰ってこないたびに、悲しい顔をするのを見てきた。ルーシーはパーティーに参加する機会はなかったけれど、心の奥底では心配しているのがわかっていた。彼女は怖がっていた。彼女は5年間救われたのは幸運だった。そう、ルーシーは私より5歳年上で、私は18歳になったばかり。18歳以上の女の子だけが寄付を許される。でも、私は何年も不安になる機会さえなかった。18歳になった途端、呼ばれたんだ。悲しくないわけがない。でも、他に何ができる? 私は選択肢がない。「エミリー? なんで泣いてるの?」 優しい女性の声が、私の悪夢のような考えから私を連れ戻した。涙で濡れた顔を上げると、ルーシーがベッドから起き上がり、心配そうな表情で私を見て、私の顔を優しく撫でていた。彼女を見て、さらに涙がこぼれた。私は彼女を強く抱きしめた。「ルーシー! 行きたくない!」 私はしゃくりあげながら言った。「どうしたの?」 彼女は不安そうだった。震える唇を開き、私は言った。「パーティー。今年、私たちを招待したの。」
その言葉は、ルーシーの喉に冷水を注ぎ込んだようだった。彼女の衝撃的な表情が悲しみに変わり、涙が目じりからこぼれ落ちるのが見えた。「嫌!」 彼女は私を強く抱きしめた。「嫌!」
その夜、私たちはグランプスが心配してドアをノックしても、夕食に降りなかった。ルーシーも私も、何も食べる気分じゃなかった。暖かい毛布の下に寄り添い、目を腫らすまで泣いた。「ルーシー、どうしてこんなことが私たちに起こるの? 街にはたくさんの女の子がいるのに、なんで私たちなの?」
「わからない、エミリー。泣かないで。」 彼女は私の涙を拭った。「この日が来ることはわかってたけど…」
「お姉ちゃん!」 私は彼女を見た。「どうして、今まで選ばれなかったの? 何か言ったんでしょ?」
「わからない。ただ、一日中部屋に隠れてただけ。目立ちたくなかったの。どうして今年、私たち二人を選ぶのかわからない。」
「あなたはどうなるの? グランプスは?」 別のすすり泣きが私の口からこぼれ、ある考えが頭に浮かんだ。私は口に出した。「逃げよう。」
「グランプスは確かに一人になるけど…」 ルーシーは顔を拭い、私を厳しく見つめた。「エミリー、何か約束して。」
「なに?」
「グランプスのために逃げないって約束して。勇敢に立ち向かうって約束して。」 彼女は震える息を吸い込み、私の頭を撫でた。「一緒にパーティーに行こう。」
私は唇を噛み、うなずいた。しばらくの間、私たちは二人とも沈黙していたが、透明な窓から明るい月光が部屋に差し込んだ。私たちは夕方から真夜中まで泣き続け、今は目が麻痺しているように感じた。どうすればいいんだろう? 未来を変えることはできない。もう泣いても意味がない。誰も私たちを守ってくれない。私は妹を見て、彼女は横向きにぐっすり眠っていた。彼女の青白い顔と涙で濡れた頬は、月光の中で輝いていた。彼女は正しかった。たとえ闇に落ちても、一緒にいて、困難に立ち向かわなければならない。ルーシー、パーティーではあなたを失望させないよ。私は勇敢になる! その後、私の目は閉じ、私は眠りに落ちた… 眠っていたのか、そうでないのか、悪夢だったのかどうかもわからなかったが、突然、暗い部屋にいることに気づいた。私は服を着ていなかった。部屋の隅に移動し、冷たい壁に寄り添った。突然の冷たさで、背筋に悪寒が走った。私は自分を抱きしめ、全身に鳥肌が立った。何かする前に、足音が耳に響いた。その音はどんどん近づいてきて、私の目の前に誰かの暗い足の輪郭が見えた。私は冷たさを無視して、壁に縮こまった。その人は私の行動に気づいたようで、私の手首を掴み、私の裸の体を自分の方に引っ張った。手が私を抱きしめ、彼の唇が私の温かい肌に触れた。私は震え、自分の弱い手でその男を突き放した。この人は変な人みたいだった。彼の胸が人間のようには上下していないのが感じられなかった。彼の体はまるで氷に触れたかのように冷たかった。でも、私の行動はすべて無駄だった。彼は大きな手で私の手を抑えた。何か考える前に、私は首に鋭い痛みを感じた。二つの尖った歯が私の滑らかな肌の表面を裂き、血管につながり、血を吸い始めた。私は叫んだ。蹴った。突き飛ばした。でも、何も起こらなかった。吸い込みが続くにつれて、鋭い痛みは増した。私の体はゆっくりと弱り、恐怖が私の視界を覆った。私は死ぬのだろうか? このまま? ヴァンパイアに行くのは良い考えじゃなかったとわかった。私の体はゆっくりと弱っていくのを感じた。痛みさえ麻痺した。もう何も感じることができず、私の手足は男の腕の中でぐったりとした。私の半開きの目は、暗い影を見つめていた。何も見えなかった。視界がぼやけ、私は目を閉じた。私の浅い呼吸はとてもゆっくりで、胸が上がっているのさえ感じられなかった。私は死ぬんだ。男は私の体の最後の滴を吸い込み、歯を引っ込め、口を拭った…。「あ!」 私は叫び、目を開けた。私の手は首に触れ、滑らかな肌を感じ、肩の力が抜けた。私の目の前には、まだ自分の部屋が見えた。「エミリー、どうしたの?」 ルーシーが尋ねた。「私…」 私は彼女に、ヴァンパイアの悪夢を見たなんて言えなかった。そんなことしたら、彼女はもっと怖がるだろうから。
「虫を見たんだと思う」 嘘をついた。ルーシーがリラックスして首を横に振るのが見えた。「びっくりしたわ」
「ごめん」 私は毛布を押し戻した。「トイレに行かなきゃ」
どうせ眠れない。散歩でもしよう。ドアを押し開けて階下へ向かった。リビングに入ると、見慣れた姿が目に入った。窓からそう遠くないところに座り、空を見つめている。「グランプス?」
彼は私の方を向き、弱々しく微笑んだ。「寝てないのかい、お嬢さん?」
「グランプスはなんで寝てないの?」
「過去のことを考えていたんだ」
どんな過去?「座らないか?」 彼は向かいの席を指し示した。「君に話したいことがあるんだ」
私は静かに歩いて行き、座った。真夜中にグランプスが何を話したいのか分からなかった。「私が君くらいの年齢の時、ある人に会ったんだ。彼女は素敵な女の子だった。私が仕事に行くとき、毎日寂しそうな女の子の姿を見たのを覚えている。彼女はただ立って、憧れの眼差しで私を見ていたんだ。私が近づいてデートに誘ったとき、最初は断られた。悲しかったけど、無理強いはしなかった。でも、その後も彼女は小屋の下に隠れて、太陽から身を隠し、私が仕事をしている間、私を見ていたんだ」 グランプスはため息をつき、窓の外を眺めた。「それから、私は自分を抑えきれず、心を込めて彼女を追いかけた。彼女は最終的に同意してくれた。私たちは普通のカップルになると思っていたけど、彼女が普通じゃないなんて誰が知っていたことか」
「普通じゃない…」 私は最後の三つの言葉を繰り返し、グランプスが何を言おうとしているのか薄々察し、怖くなった。「そう、彼女はヴァンパイアだったんだ。一度、森の中で彼女が動物の血を飲んでいるのを見たんだ。私たちは言い争って…」
「うまくいかなかったんでしょ?」
「まあ、しばらくはうまくいったんだ。私たちは一緒にいられて、本当にカップルになれた。でも…運命は私たちを一緒にいることを望まなかったんだ」 グランプスの目には、そう言うとき、寂しさが滲んでいた。私は彼に何があったのか、なぜ一緒にいられなかったのか尋ねたかった。でも、彼の表情を見て、言葉を飲み込んだ。もしかしたら、彼女がヴァンパイアだったからうまくいかなかったのだろうか?どうやったらうまくいくんだろう?一方は獲物で、もう一方はハンターだ。食べ物と空腹な人の間に友情はありえない。「エミリー」 彼の掠れた声が言った。「ただ伝えたかったんだ、ヴァンパイアがみんな殺人者というわけじゃないって」