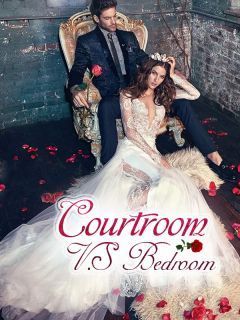紹介
目次
紹介
ジュリエットの人生が下降線をたどる中、彼女はあらゆる場面で現れる謎のストレンジャーに気づき始める。彼らを引き合わせるのは偶然か、それとも運命か?二人の道が交差するにつれ、ジュリエットはこの謎めいた人物に惹かれていく。彼はまさに彼女が助けを必要とするときに現れるのだ。しかし、彼は一体何者なのだろうか?そして、一連の偶然の出会いは、それ以上のものにつながるのだろうか?それとも、彼女は予想以上のものを見つけることになるのだろうか?
もっと読む
すべての章
目次
1
3
第4章
6
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
32
33
34
35
36
37
38
39
40
42
43
46
47
48
49
50
51
53
55
56
57
58
59
60
62
63
64
65
66
68
71
72
73
74
75
76
77
78
79
81
82
83
84
85
86
87
88
90
91
92
94
95
96
97
98
99
100
101
102
104
105
108
109
110
111
112
113
115
117
118
119
120
121
122
124
125
126
127
128
130
133
134
135
136
137
139
140
140
141
143
144
145
146
147
148
149
150
152
153
154
156
157
158
159
160
161
162
163
164
166
167
170
171
172
173
174
175
177
179
180
181
182
183
184
186
187
18
52
80
114
142
176
Eight
41
70
103
132
165
31
93
155
Seven
44
69
106
131
168
54
116
178
45
61
107
123
169
185
67
89
Two
27
151