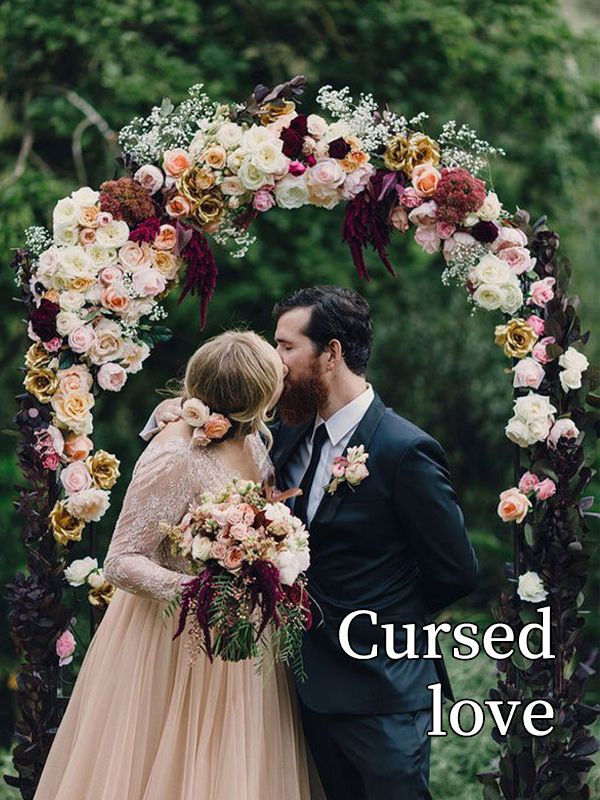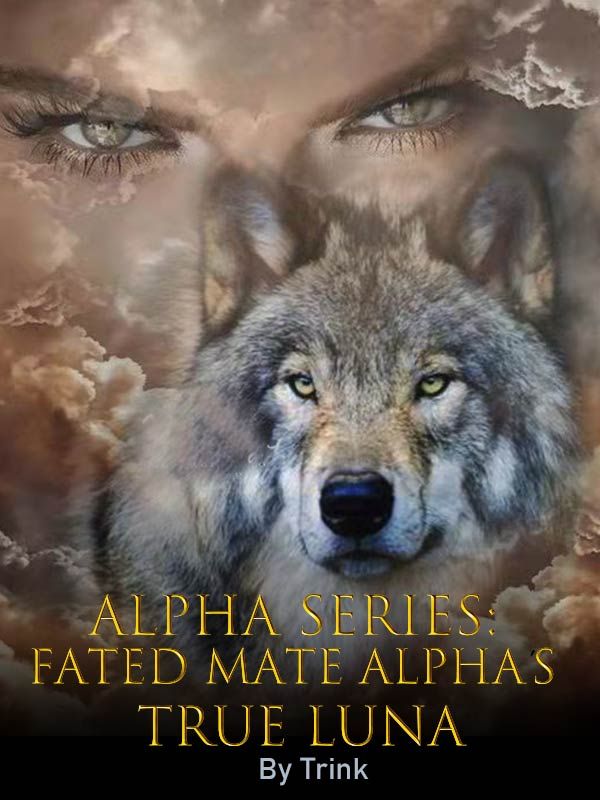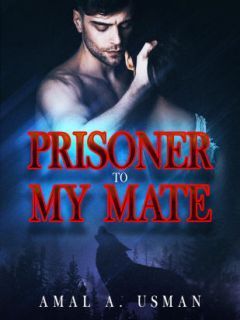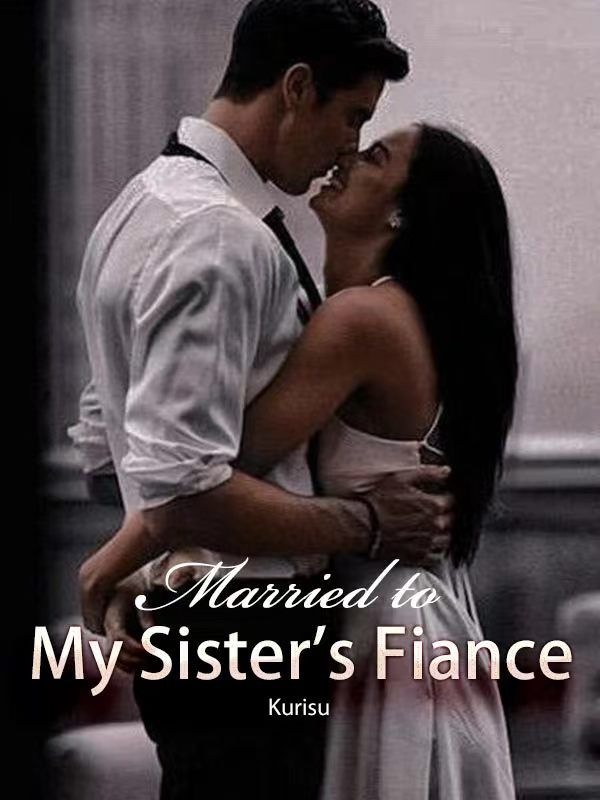生足が、分厚い森のデコボコの地面を叩きつける。荒い息遣いが、夜の静けさ、ってやつをぶち壊してる。彼女が息を止めるたびに、フクロウのホーホーって鳴き声がはっきり聞こえるんだ。コオロギたちは、まるで自分たちの縄張りを取り囲むカオスに気づかないように、陽気に歌ってる。
振り返ると、彼女を追いかけてくるヤツのデカいシルエットが見えた。破れたブラウスをぎゅっと掴んで、彼女はみっともなさから自分を守ろうとした。全部奪われた後なのに。
涙で濡れた頬は、彼女が直面した恐怖、というか、まだ耐え忍んでいるものの明確な証拠。
「神様、どうか助けてください」彼女は、分厚い葉っぱの中にむやみに走りながら、何度もつぶやいた。
死が彼女の救世主だとしても、彼女は気にしなかった。あの瞬間に、ただ平和が欲しかったんだ。
立ち止まって休みたいけど、それは負けを意味する。それは弱いってことなんだ。
彼にそんな満足感を与えるわけにはいかない。
枝が彼女の肌を引っ掻き、彼女は走り続けた。彼女の足は、裸足に与えられた拷問を訴えてる。肺は、必要な空気を求めてるけど、彼女はすべてに屈しないと決めたんだ。
振り返ると、彼女は転倒させた根っこを予測できなかった。這い上がると、彼は怒って名前を叫んだのが聞こえた。明らかにイライラしてるか、疲れてるか。
足に走る痛みは、彼女を激しい動きから動けなくし、彼女は開口部に向かってよろめかざるを得なかった。ついに、奇跡的に開けた道にたどり着いた。
2つの光線が彼女を眩ませ、彼女は道の真ん中で凍りつき、光の光線から目を守った。
「今すぐ私を連れて行って」彼女は心の中で思った。あのモンスターに直面するよりマシだ。
タイヤのキーキー音は、車が彼女からわずか数インチのところで止まったことを示していた。
屈強な男たちが車から降りてきて、彼女を威圧するように見ていた。銃が彼女の方向に向けられた。
「こんな不吉な時間に、私を止めるのは誰だ」と声が響き渡ったのが聞こえた。
この声に構わず、彼女はさっき出てきた茂みに目をやると、彼が闇に後退していくのが見えた。
「誰も答えないのか」前の声が怒ってうなり声を上げ、彼女は声の厳しさにたじろぎ、恐怖で目を大きく見開いた。
彼女の最初の考えは、彼女は地獄から逃れて別の地獄に入ったということだった。彼女の視界を遮る2人の警備員が脇に退いたからだ。
彼女の前にいる男を見ると、彼女は息を呑み、ひざまずき、額を地面につけて謝罪の言葉をつぶやいた。
「陛下、どうかお許しください」彼女は泣き叫び、彼が望めば一瞬で彼女の命が奪われるかもしれないので、あの男たちをあえて見上げようともしなかった。
「なぜ私の行列を宮殿で止めたのか。どんな罰を受けるべきだと思うか教えてくれ」と彼は言い、彼女は彼の足元を見た。
「私の王が相応しいと思うどんな罰でも」彼女は恐怖で震えながらささやいた。
「立ちなさい」と彼はうなり声を上げた。
シャツをきつく掴み、彼女は痛みを隠そうと立ち上がった。
彼女の前に立っていると、彼の視線を感じた。彼女は無礼だった。目を固く閉じて、これがすべて悪い夢であることを祈った。
彼が次にしたことは彼女を驚かせ、さらに警備員を驚かせた。
「私を見ろ」彼は命じた。
「お許しください」彼女は何を聞いたのかわからず、ささやいた。
「見ろ。私を」彼は一言一言ゆっくりと、はっきりとそう言った。
そう言われた通り、彼女は彼の茶色の目を見た。彼の顔は花崗岩のように硬く、彼の顔は彼女を見てどんな表情も消されていた。
「車に乗れ。私のスタッフがあなたを綺麗にしてくれるだろう。それから、休んだ後で、あなたにふさわしい罰を見ることができる」と彼は言った。王が車に向かって歩き出したとき、警備員が彼女に向かって近づいた。
荒々しく彼女の腕を掴むと、彼女は痛みで顔をしかめたが、王室の高貴な方はすぐに止まり、警備員を警戒して見つめることで、そのプレッシャーは一瞬でなくなったのを感じた。
3台目の車に向かって足を引きずり、ついに足から解放されたことに感謝して後部座席に座った。ドアが開いて、王自身が現れ、彼女の隣に座った。彼は、気が向いたらすぐに車から彼女を投げ出すのではないかと恐れて、彼を見ないように頭を下げていた。
交差点で車が止まった衝撃で、彼女はシートベルトが彼女の肌に食い込み、痛みに顔をしかめた。
「次にお前がこの車をバカみたいに止めたら、それが最後だ」と彼は車の中で響き渡り、その厳しさに彼女はたじろぎ、シートベルトの留め金を押し、セキュリティから解放した。
彼女が恥ずかしさを隠そうと努力したとき、彼女の眉毛にすぐに汗が滴り落ちた。
宮殿に到着すると、彼女はジョンという名前の男に案内され、すべてのメイドが寝ているスタッフクォーターに案内された。
-----
「おかえり、愛しい人」と女王は夫に微笑んだ。
「ありがとう」彼はうんざりした様子でつぶやき、イライラした様子でネクタイを外した。
「ロンドンからの帰り道で何か問題はなかった?」
「全くない。新しい女の子を連れてきた。彼女は少し休む必要があるかもしれない。彼女の世話を頼むよ」と彼は心配そうに言い、表情を冷たくした。「出ていくときはドアを閉めて」彼は平坦な口調で言った。
女王は、夫が浴室に向かう途中で心配している兆候を見逃さず、このいわゆる女の子に腹立たしく、そして興味を持った。
----
朝の太陽は、小さな窓から太陽の光線を落とし、彼女はベッドにじっと横たわっていた。彼女の体は汗まみれで、彼女は起き上がろうとすると痛みで顔をしかめ、めまいがして倒れざるを得なかった。
「彼女はどこにいる?」彼女は、彼女の頭痛の強さを示すように、以前の夜のシルエットを見たドアが壁にバタンと閉まる音が聞こえた。彼女はすぐに恐怖に襲われ、パニックに呼吸が速くなった。
「医者は彼女の健康状態を見ていないのか?」彼は、他のメイドが入り口に立っていると、怒鳴った。
「答えて!」彼は叫び、彼らは恐怖で飛びのいた。
「女王様が彼を要求されました」と女の子の一人が口ごもり、彼は彼女を観察して目を細めた。
「私のために電話をしろ」と彼は危険なほど低い声で言い、その女の子は医者を探しに急いで去った。「他の人に玉座の間で会えって伝えろ」と彼は警備員の一人に言った。
若い女の子の方を向いて、彼は簡単な質問をした。
「あなたの名前は?」
「大きな声で言え!」彼は彼女が話そうとするところを見て、彼女が明らかに飲み込んだと言った。
彼女は名前をつぶやくことしかできず、彼女が話すことを強制することは無意味だと見て、彼女の唇に向かって頭を下げざるを得なかった。
「ルード」彼女はささやき、疲れ切って見える目を閉じた。
「あなたとあなた」彼女が回復した後、彼女があなたの一人として任務を再開するように、彼女は十分な世話を受けるようにしなさい、私が明確にしているかどうか?」彼は響き渡った。
「はい、陛下」彼らは恐怖で頭を下げ、彼を去らせた。