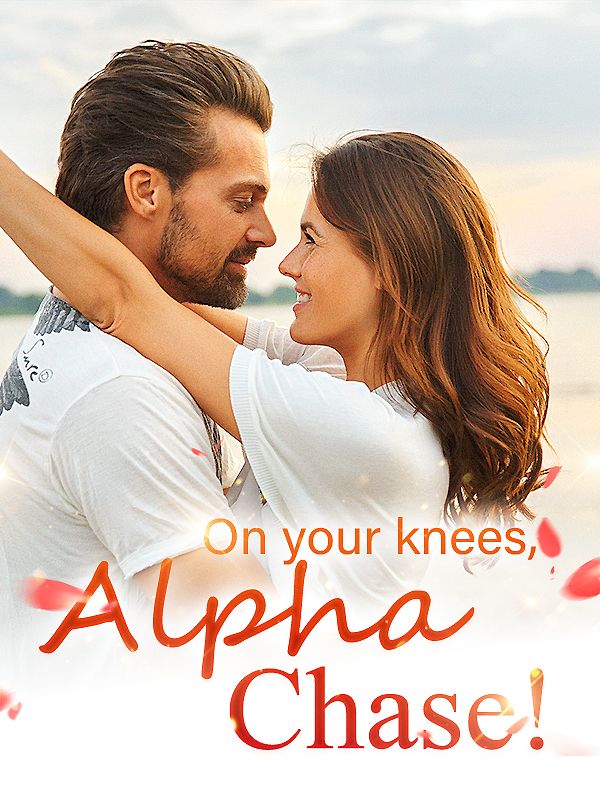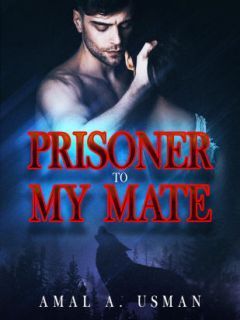二週間前。
「私の服、大丈夫かな?」と、私は過去三分の間に十回もフェイスに不安そうに尋ねた。
私は、可愛らしい膝丈の白いワンピースを着ていて、それにピンクの小さな花がついていて、さらに合うピンクのセーターを重ね着して、もっときちんと見えるようにした。靴は白いスニーカーを選び、髪はゆるいカールにした。
「ハンナ、めっちゃ似合ってるよ」フェイスは心からそう言って、私の椅子から小さく微笑んだ。
「うん、チャドリーがそう思わないなら、マジで目が見えてないんだよ」ベイリーが、私のベッドの上で適当なファッション雑誌を読みながら口を挟んだ。
チャドリー・ハンティントン。
チャドって呼ばれてる。
チャドと私は、付き合ってから十ヶ月になる。
今日は私たちの十ヶ月記念日で、私は彼に野球のチケットをサプライズであげるという、勇気ある決断をしたんだ。
彼は野球オタクだから、それに合うプレゼントをあげたかった。
私の部屋のドアをノックする音が聞こえ、開くと、ハンナの母が現れた。
「準備できた?」と彼女は笑顔で尋ねた。
私はうなずき、不安そうに自分のバッグを掴んで、友達にさよならを言った。彼女たちも私に手を振り、私は部屋を出た。
全部計画通りに進むといいな。
-
「後で迎えに行こうか?」と、私のハンナの母がシートベルトを外しながら私に尋ねた。
私は一瞬チャドリーの家を見てから彼女の方を向き、首を横に振った。
「ううん、たぶん彼のママが送ってくれると思う」と私は答えた。彼のママはいつも私を家まで送ってくれるのをかってでてくれるから。
もし彼女が私を送る気がないなら、私のハンナの母に電話することもできる。
「わかった。もし迎えが必要になったら電話してね」彼女は真剣な口調で言った。
私のハンナの母たちは誘拐にものすごく神経質なんだよね。
私や兄弟は、他の信頼できる大人がいない限り、九時過ぎには外出させてもらえない。
でも、彼女たちの心配はわかるんだ。
「わかった」私は感謝の笑顔で答え、車から降りた。
私はドアを閉め、石畳の小道を歩きながら、彼らの玄関に向かった。
玄関の前に着くと、三回ノックして数秒待つと、ハンティントン夫人の興奮した表情が現れた。
「ハンナ!」彼女は明らかに嬉しそうに叫んだ。
「こんにちは、ハンティントン夫人」と私は笑顔で言った。
彼女は脇に寄り、私が家に入れるようにした。私は抵抗せずに家に入った。彼女はすぐにドアを閉め、秋の風が暖かい家に入らないようにした。
「チャドリーは二階の自分の部屋にいるけど、私が連れて行く?」彼女は丁寧に尋ねた。
「いいえ、一人で行っても大丈夫?」と私は尋ねた。
彼女はすぐに首を振り、手で私を階段の方へ促した。私はお礼を言い、ボーイフレンドの部屋に向かった。
彼の部屋に近づくにつれて、奇妙な音が聞こえてきた。
まさか彼のゲームの音?
彼はしばらくゲームしてないし。
彼のテレビ?
彼は普段ケーブルテレビは見ないし。
部屋の外に出ると、私はその音を完全に聞き取ることができた。
彼はポルノを見てるんだ。
なんでポルノを見てるんだ?
私は彼のドアノブを回し、ドアを開けると、すぐに目に飛び込んできた光景に足を止めた。
信じられない。
こんなことってある?
「まじかよ」と私は衝撃的な口調で言った。
私の親友は、私の声に驚いた表情で、ボーイフレンドの上から飛び降りた。
まさか。
お願い、こんなことってないって言って。
「ハンナ、これは見た目ほどのことじゃないんだ」チャドリーは、ズボンが膨らんだ状態で立ち上がり、弁解しようとした。
私は親友の方を見た。彼女は、私の両親と私が喧嘩した夜に私が一緒に寝たのと同じ毛布を使って、体を隠そうと試みているが、うまくいっていない。
「ボーイフレンドと親友に浮気されたみたい」と私は少し掠れた声で言った。
私は彼のために戦うつもりはない。
明らかに、私たちの関係は、彼にとって私にとってほど重要ではなかったんだ。
だから、もう終わり。
「あー、じゃあ、まさに見た目通りね」と私の親友は言った。
「うるさい、アヴァ」チャドリーは彼女に不機嫌そうに言った。
私はため息をつき、冷静に彼に野球のチケットを手渡した。もう私には必要ないから。
「十ヶ月記念日おめでとう」と私は、少し昔を懐かしむ笑顔で言い、彼の部屋から退散した。
「ハンナ、待って!」彼は私を呼んだが、私は歩き続けた。
「いいよ、ベイビー。遅かれ早かれ、彼女は気づくことになるんだから」アヴァは彼に不機嫌そうに言った。
自分がこんなにバカだったなんて信じられない。
どうしてサインに気づかなかったんだろう?
学校で彼と私が一緒にいるときはいつもお互いにメールを送っていた。
私たちの関係の節目について私が話すたびに、いつも嫉妬していた。
いつも秘密を持っていた。
「ハンナ、大丈夫?」ハンティントン夫人は、私がタイルの床に足を踏み入れたとき、困惑した表情で私に尋ねた。
私はすぐに涙を拭い、うなずいた。
「うん」と私は小さく微笑んで答えた。
「チャドリーは何か同意なしにしたの?」彼女は明らかに不安そうに尋ね、私は小さく笑った。
私は本当にハンティントン夫人のことと、彼女の絶妙なベーキングスキルを恋しく思うだろう。
「私はあなたの息子を愛していたけど、今夜、彼は私の心を傷つけたの」と私は、彼女に正直に、憎しみや悪意のない口調で答えた。
「あらまあ、大変ね」彼女は心配そうに言った。
「大丈夫よ。あなたが最悪なことを想像しないように、ただ伝えたかっただけ」と私は彼女に言った。
彼女は寄り添い、私を巨大なハグで包んだ。私は逃げなかった。実際、彼女のハグに慰めを感じた。
ハグから離れると、チャドリーが二階から叫ぶのが聞こえた。
「ハンナ、待ってくれ、説明できるんだ」彼は恐ろしい口調で懇願した。
私は彼に心からの笑顔を向け、ドアノブを握った。
「さようなら、チャドリー」と言って、私はハンティントン家を出た。
私はすぐに小道を走り抜け、通りに向かった。ポケットから携帯電話を取り出し、私のハンナの母の番号をダイヤルした。
電話が鳴り始めると、涙が目に滲み、頬を伝ってすぐに流れ落ちた。
「もしもし?」私のハンナの母がショックした口調で答えた。
「ママ、私、間違えちゃった。迎えに来てくれる?」と私は、泣きながら尋ねた。塩辛い涙でドレスがびしょ濡れになった。
-
「ハンナ、すごくつらいのはわかるけど、お願いだからメイクを落とさせて」ベイリーが私のベッドの左側から懇願した。
ベイリーは将来皮膚科医になりたいと思っていて、誰かが肌の手入れをしていないとすごくイライラするんだよね。
一時間も彼女の文句を聞かなくて済むように、私は彼女にメイクを落とさせることにした。
「アイスクリーム食べる?」フェイスが、ベッドの上で私を見ながら、優しく私の金髪を撫で続けて尋ねた。
私はベッドの上から彼女を見上げ、うなずいた。彼女は私に微笑み、部屋を出てドアを閉めた。
彼女がいない間に、ベイリーはメイク落としを始めた。
正直、もう何年も寝ていたい。
ベイリーがメイクを落とし終わるとすぐに、ドアをノックする音が聞こえた。見ると、私の両方のハンナの母が悲しそうな表情でドアのそばに立っていた。
「私は邪魔しないわ」ベイリーは笑顔で、親指で私の肩を優しく撫でながら言った。
彼女は自分のバッグを取り、すぐに部屋を出た。彼女が完全に部屋から出ると、私の両親は中に入り、ドアを閉めた。
彼女たちは沈黙したままで、私の体の両側に座った。
「彼は浮気したの」私は、彼女たちが尋ねなかった質問に答えた。
私のハンナの母はゾッとした表情で、私のハンナの母は殺人的な表情をしている。
二人はお互いを見て、目だけで会話しているようだった。
「アヴァと浮気したの」と私は付け加えた。
彼女たちの目はほとんど同時に見開かれた。
「シャーロット!」私のハンナの母が、困惑した口調で叫び、彼女の肩を叩いた。
彼女たちの考えていることが聞こえなくて本当に良かった。
「ハンナ、学校を少し休みたい?」私のハンナの母が、私のハンナの母から視線をそらしながら私に尋ねた。
私は、彼女たちの睨み合いに巻き込まれたくなかったので、うなずいた。
彼女たちは私の答えにうなずき、再び悲しそうな笑顔で、私の頭の両側にキスをした。
「もしよければ、お昼寝したいんだけど、疲れちゃった」と私は小さく微笑んで彼女たちに言った。
「わかったわ。何か必要になったら呼んでね」と私のハンナの母が、私のハンナの母と一緒に部屋を出た。
あーあ。
今日は、私が望んでいたようには何一つ進まなかったけど、アヴァは正しかった。
私は、遅かれ早かれ、彼らの秘密の事件について知ることになっていたんだ。
ため息をつき、靴を脱いで、毛布の下に滑り込んだ。
もしかしたら、眠ってしまえるかもしれない。
-
アスペンの視点
「彼女のこと、本当に気の毒だわ」シャーロットと私がキッチンに向かう階段を下りながら言った。
「私もよ。でも、私たちにできることはあまりないわ。この別れが、彼女を苦しめるに任せるしかないのよ」彼女はそう言って、私をバースツールに置き、ワインを取りに行った。
「別れに関する経験がもっとあれば、彼女に適切なアドバイスができるのに」と私は座って、シャーロットがグラスにワインを注ぐのを見ながら言った。
彼女は私の言葉に緊張し、すぐに注ぐのをやめた。
「ベイビー、あなたの気持ちはわかるわ。本当にそうよ。でも、別れに対する対処法は、人それぞれ違うものなのよ」シャーロットはそう言って、私にワインのグラスを滑らせた。
私はうなずき、人差し指でグラスの縁をなぞった。
「アマンダはどうしてる?」と私はシャーロットに尋ねた。
アマンダは、シャーロットのグループに入ったばかりなんだよね。
彼女は、シャーロットと私が養子縁組を決める前に住んでいた家に住んでいるんだ。
彼女は本当にいい人で、娘さんもいるの。
オーレリアだっけ?
「昨日話したんだけど、うまく馴染んでいるみたい。オーレリアもトレーニングを始めるのが待ちきれないって言ってたわ」シャーロットが答えた。
私はこの情報に微笑んだ。
「それは素晴らしいわね!そろそろ彼女たちに会いに行く?」と私は尋ねた。
彼女は肩をすくめ、ワインを一口飲んだ。
「電話して聞いてみたら?きっと嫌がらないと思うわ」シャーロットが答えた。
「そうね、そうするわ」と私は答え、バースツールから立ち上がり、携帯電話に向かった。