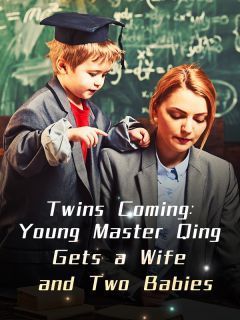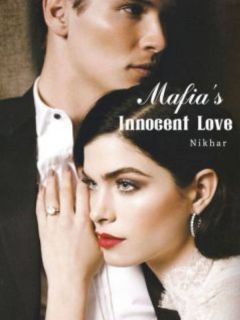ニューヨーク、ミア。
病院は嫌い。病気になるのも嫌い。医者に行くのも嫌いなんだよね。あたしだったら、もう健康なんて窓から投げ捨てたいくらい。
ドクター・ブリンを見て、吹き出しちゃった。ドクター・ブリン、塩胡椒の髪で、鼻の上にはメガネをかけた、ちょっと怖い感じの中年男性。あたしを見て、眉毛を上げた。「何がおかしいんですか、ミズ・アンダーソン?」って聞いてきたけど、ちょっとだけ興味と、ちょっとだけイライラしてる感じ。
笑いが止まらなくて、お腹の底から込み上げてきて、肩が揺れて、笑いすぎて鼻からフガッて出ちゃった。マジで、あの時は全部面白かったんだよね。緊張とか、信じられない気持ちとか、あと、あたしの中に変なユーモアが生まれてたんだよね。
「そのうち、赤ちゃんを産む時に、こんな風に笑えなくなるでしょうね」ってドクター・ブリンがちょっとニヤけながら、ごちゃごちゃした予定表に何か書き込んでた。それ見て、さらに笑っちゃって、涙が頬を伝った。
「赤ちゃん産む気ないから、笑わないと思う」って、笑いながらも、どうにかこうにか言えた。目尻の涙を拭いながらね。もう、この状況が現実味なさすぎてヤバかった。
ドクター・ブリンは真剣な顔になって、あたしをじっと見つめてきた。「中絶するつもりですか?」って、優しく、でも探るように聞いてきた。「大きな決断だし、何かあったら相談に乗りますよ」
あたしは信じられなくて、笑いも収まって、混乱と信じられない気持ちが押し寄せてきた。この人、何考えてんの?「中絶するつもりなんてないです」ってきっぱり答えた。「先生、どんな薬やってるのか知らないけど、あたし妊娠できないはずなんです」あたしはバッグに手を伸ばして、早くこの変な状況から抜け出したい気持ちがどんどん強くなってた。あのオフィスに長くいるほど、全部面白くなってくるんだよね。
ドクター・ブリンは身を乗り出して、もっと心配そうな顔になった。「ミズ・アンダーソン、薬やってるのは、あなたの方じゃないですか?」ため息をついて、あたしの精神状態を心配してるみたい。
あたしは首を振って、どうにか落ち着こうとした。「妊娠できないんです、先生。結婚前の検査で、不妊だって言われてたんです」『不妊』って言葉が、すごく嫌な感じ。「つまり、あたしは子供を産めないってことなんです」ここで、なんか胸が締め付けられた。すごい嫌な気持ち。
「あたしは医者です、ミズ・アンダーソン。そんなことも知らなかったら、ここで落ち着いて座ってませんよ。その検査では、あなたとパートナーの間で、不妊の可能性があるってだけだったんです」ドクター・ブリンは落ち着いた口調で繰り返した。「今、あなたが妊娠してるってことは、たぶん問題は、あなたの元パートナーの精子の質にあるんですよ。あなたは、全然妊娠できるんです、ミズ・アンダーソン」
あたしは、自分が何を聞いているのか信じられなかった。まるで地面が揺れて、足元が定まらない感じ。つまり、今まで、不妊の原因は、あたしの元旦那だったってこと!?最悪の展開で、あたしは色んな感情が入り混じって、変な気持ちになった。
「マジで冗談でしょ、先生」あたしの感情がぐるぐる渦巻いて、ショックからり、悲しみ、全部がごちゃ混ぜになって、どれが一番強いのか分かんなかった。
ドクター・ブリンは、いつものように冷静な感じで、深呼吸をした。「ミズ・アンダーソン、あたしはもう10年以上この仕事してるんです。今あなたが感じてる、この感情のジェットコースターみたいなの、それは妊娠ホルモンが働いてるんですよ」
まだ頭がぼーっとしてて、全部を理解しようとしてた。「つまり、今まで、不妊の原因はあたしじゃなくて、元旦那だったってこと?」なんか、カタルシスを感じてる自分もいた。あたしの人生に、カルマが介入してきたみたいな感じで、変な満足感があった。
ドクター・ブリンは首を振って、同情するような顔をした。「ええ、彼はかなり問題でしたね」って確認した。「あなたの元パートナーの精子の質に問題があるってことは明らかです。あなたは、全然妊娠できるんです、ミズ・アンダーソン」
「マジで、カルマって最高じゃん」って小声でつぶやいたら、口元がちょっと緩んだ。ドクター・ブリンは、「マジかよ?」って顔で見てきた。あたしの変な反応にも関わらず、プロ意識は揺るがない。
「ミズ・アンダーソン」って、優しくもきっぱりと言った。「そろそろ家に帰って、パートナーにこの家族の新しいメンバーについて話す時ですよ。次の予約は、1ヶ月後にしましょう」
パートナー。妊娠。その考えが頭をぐるぐる回って、髪の毛をむしり取りたくなった。「うー」って唸って、苛立ちを抑えきれなかった。
ドクター・ブリンは、あたしの突然の困惑に興味を持ったのか、眉を上げた。「今度は何ですか、ミズ・アンダーソン?」ため息をついて、この奇妙な話の、また予想外の展開に備えてるみたい。
「ワンナイト・ラブだったんです」って、止める間もなく、言葉が口から飛び出した。ドクター・ブリンの顔は、好奇心から、ちょっと不快そうな顔に変わった。
彼は、あたしの話を聞きたくないかのように、手を上げた。「単なる社交辞令で聞いただけで、あなたの…夜の冒険について聞きたかったわけじゃないんです」そう言って、彼はそそくさと部屋を出て行った。あたしは、自分の心の中の騒ぎと、予期せぬ妊娠という新しい現実に、一人取り残された。
ドクター・ブリンのオフィスを出た後も、その衝撃的な事実が重くのしかかってた。自分が妊娠していて、不妊の原因があたしの元旦那だったっていうニュースは、あたしに色んな感情を巻き起こした。でも、あたしの頭の中の混沌の中で、もう一つの力が現れ始めた。まるでゆっくりと押し寄せる波のように。
ワンナイト・ラブの記憶が、あたしの頭の中で蘇り始めた。最初は、地平線上の遠い雷のような、かすかな閃きだった。でも、一歩踏み出すたびに、息をするたびに、その記憶は強くなり、鮮明になり、あたしを津波のように飲み込んでいった。
あの夜のことを、まるで絶対に止められない映画のように、あたしは頭の中で何度も再生していた。それは、あたしのクライアントの結婚式で起きたことだった。あたしが、誰の腕の中でもなく、新郎の弟の腕の中に安らぎを求めた夜、あたしが、警戒心を捨てて、その瞬間の熱の中に溺れることを許した夜。
セバスチャン・ソーントン。億万長者。アメリカで一番の独身男性。あたしのクライアントの義理の兄弟。あたしのベイビーダディ。