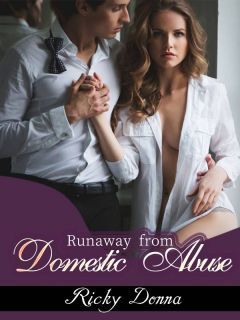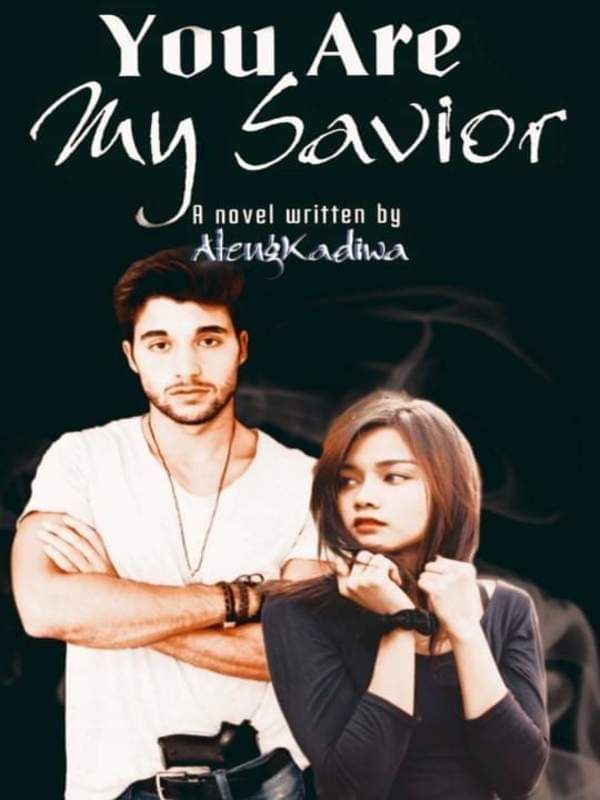紹介
目次
紹介
「明るい面を見て目を痛めた人なんていないわ」と私。
「そうですね、今日はメガネがすごく必要だとお知らせしなければなりませんね」と彼は答えます。
*******
ロレイン・スチュアートは、ごく普通の若い女性ではありません。双子の弟の失踪に対処し、短気なお父さんに対処しながら、その中で自分自身を見つけようと努力しなければなりません。彼女にとって、物事は間違いなく困難でした。
しかし、彼女がヘーゼル色の目をした生意気な男、アレクサンダー・ウェインと偽りの婚約をすることになったらどうなるでしょうか。彼女は彼を嫌っています。
心配しないで、お互い様です。少なくとも、彼らはそう思っていました。
感情が生まれ、秘密が解き明かされ、謎が解き明かされるにつれて、彼女は自分自身をしっかり保つことができるでしょうか。
二人は恋に落ち始めるのでしょうか、それとも単なる婚約協定なのでしょうか。
そして何よりも、嵐の直前に自分たちを守ることができるでしょうか?
もっと読む
すべての章
目次
CHAPTER1
CHAPTER2
CHAPTER3
CHAPTER4
CHAPTER5
CHAPTER6
CHAPTER7
CHAPTER8
CHAPTER9
CHAPTER10
CHAPTER11
CHAPTER12
CHAPTER13
CHAPTER14
CHAPTER15
CHAPTER16
CHAPTER17
CHAPTER18
CHAPTER19
CHAPTER20
CHAPTER21
CHAPTER22
CHAPTER23
CHAPTER24
CHAPTER25
CHAPTER26
CHAPTER27
CHAPTER28
CHAPTER29
CHAPTER30
CHAPTER31
CHAPTER32
CHAPTER33
CHAPTER34
CHAPTER35
CHAPTER36
CHAPTER37
CHAPTER38
CHAPTER39
CHAPTER40
CHAPTER41
CHAPTER42