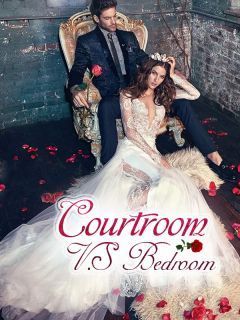カリーはセスへの愛を告白し、彼も同じように告白した。
あたしは、通り過ぎたウェイターから飲み物をサッと奪い、考えもせずにグラスを頭に持っていき、中身を全部飲み干した。友達のアイリスの方を見ると、彼女は目で部屋を見渡している。
ため息をついた。「なんでまたあたし、ここにいるんだろ?」
アイリスはスツールの上で向きを変え、あたしの目をじっと見つめた。「あたしを応援するためよ」と、少し間を置いて笑った。「それと、今夜連れて帰れるようなイケメンが見つかるか見てるの」
あたしは肩をすくめた。「今夜は男に構われたくないんだ」
「そういえば、最後にセックスしたのはいつだっけ? ああ、去年のどっかあたりね」あたしは彼女に目を向ける。「あんた、またあの電車に乗る必要があるわね。セックスレスじゃ全然楽しくないもん」
アイリスはオフショルダーのボールガウンを着ている。彼女のブロンドの髪はカールでいっぱいになっていて、肩で弾んでいる。アイリスは、男が二度見しなくてもいいタイプの女性だ。彼女の美しさは、一言「ハロー」で十分。彼女は美しい女性であると同時に、思いやりがあり、優しくて、本当に可愛い子なの。
「たぶん、あたしは幸せだよ」
あたしは幸せだ。
あたしは、ニューヨーク市最大の法律事務所の一つ、シェパード・アンド・ギルズでパートナーになったばかりだ。あたしの犬は、美しい子犬を4匹産んだばかり。女性が夢見るものはすべて持っている。まあ、少なくとも全部はね。
彼女は首を振って笑う。「幸せだと思ってるだけでしょ。あたしは、あなたが寂しいんだと思うわ。リチャードと別れてから、全然楽しくなくなったみたい」
あたしは笑った。「あの負け犬があたしの楽しみを奪ったからだよ。でも、あたしが幸せじゃないってわけじゃない」
彼女は眉を上げてあたしを見た。「セックスしてないんでしょ」
あたしは彼女に笑った。「セックスがすべてじゃないわよ、アイリス」
「ブランドンにその言葉を聞かせないでね。私たちからしたら、セックスがすべてなんだから」ブランドンは、もう4年間アイリスのボーイフレンドだ。彼らは理想のカップルだった。一緒に住み、猫と魚を飼い、家計を分担し、デートナイトを楽しんだ。もう結婚しているようなものだった。結局のところ、彼らはすでに結婚しているカップルが普通にやることをすべてやっていたんだから。
「ブランドンみたいな素敵な男性がいたら、素晴らしい体だけじゃなくて頭もいいんだから、もちろんセックスがすべてよ。それに、あなたたちは愛し合ってるんだしね。恋をしているときは違うのよ。もうセックスじゃないんだから」
彼女はテキーラを一口飲んだ。「そうね、ただのセックスじゃないわ。ハードコアなファックよ」彼女はニヤリとした。
あたしは目を回した。「そう言いたいんじゃないのよ。愛し合ってるってこと。あなたたちはそう呼んでるんじゃないの?」
「そう、そう呼んでるわ」あたしはため息をついた。
ウェイターが前に来て、もう一杯シャンパンを勧めてきた。あたしは微笑んで、トレイからシャンパンを受け取った。「ありがとう」
今度は、その飲み物を一口ずつ味わうことにした。
「ここで飲み始めてから、もう4杯目よ。今夜は酔うつもり?」
「ううん、そんなつもりじゃなかったんだけど、よく考えたら、今夜は酔っぱらってもいいかもしれない。だって明日は大変な一日になるんだから」
「大きな案件?」
「巨大案件、上院議員リードだよ」
彼女は笑った。「ごめんだけど、もう5杯くらい飲んだ方がいいと思うわ」
あたしはうなずいて同意した。モーガン・リード上院議員は、愛人の美容整形手術のために、慈善団体から500万ドルを盗んだ罪で有罪判決を受けた。彼の弁護士として、すべての証拠が彼が実際に500万ドルを盗んだことを示しているにもかかわず、彼を窮地から救うのがあたしの仕事だったんだ。
スピーカーがマイクを使い、みんなの注意を引こうとすると、騒ぎは少し落ち着き始めた。
アイリスはあたしに向きを変え、頬を赤らめた。「あたしの番よ」
「行って、輝いてきなさい」あたしは彼女の肩を叩いた。彼女は椅子から立ち上がった。
スピーカーが「昨年最も成功した女性起業家として選ばれた、アイリス・フランシスさんをステージにお迎えしましょう。この美しい女性がステージに立つので、拍手をお願いします」と言い、群衆は歓声を上げ始めた。
アイリスがステージに上がると、みんな静かになり、彼女の話を聞き始めた。彼女は笑顔で話し始めた。「今夜、この新しい事業のオープニングを祝うために、ここに来てくださった皆様に感謝します…」
あたしは笑い、彼女がステージを降りる間拍手をした。彼女が降りてくると、多くの人が彼女に話しかけようと立ち止まった。あたしは微笑み、他のことに注意を向けた。部屋を見回して、知り合いがいないか探すと、いた。でも、あたしが好きじゃない人たちだったから、飲み物を飲み続けた。
「やあ」
あたしは声のする方へ顔を向けた。「やあ」
「マークです。フランシスさんの友達みたいですね。あなたもビジネスの世界にいるんですか?」
この会話がどういう方向に向かっているのか、あたしは気に入らなかった。実際、この会話自体が嫌だった。
「いいえ、違います。ただの普通の女です」
彼はニヤリとした。「あなたは普通の女じゃないよ」彼は誘惑しようとしていたけど、うまくいってない。あたしはそういう男たちには慣れてしまった。彼らはあたしを動揺させる能力がない。会ったときに好きになれない人は、絶対に後で好きになることはない。
「そうね。あたしは片目しか見えないし、死にかけていたおばあちゃんに腎臓を一つあげなきゃいけなかったのに、結局死んじゃったから、良い腎臓を一つ失ったの」あたしは泣きそうな顔をした。「本当に大好きだったのよ、おばあちゃんは本当に素晴らしい女性だった」あたしはすすり泣いた。「そうね、あたしは普通じゃないわね」