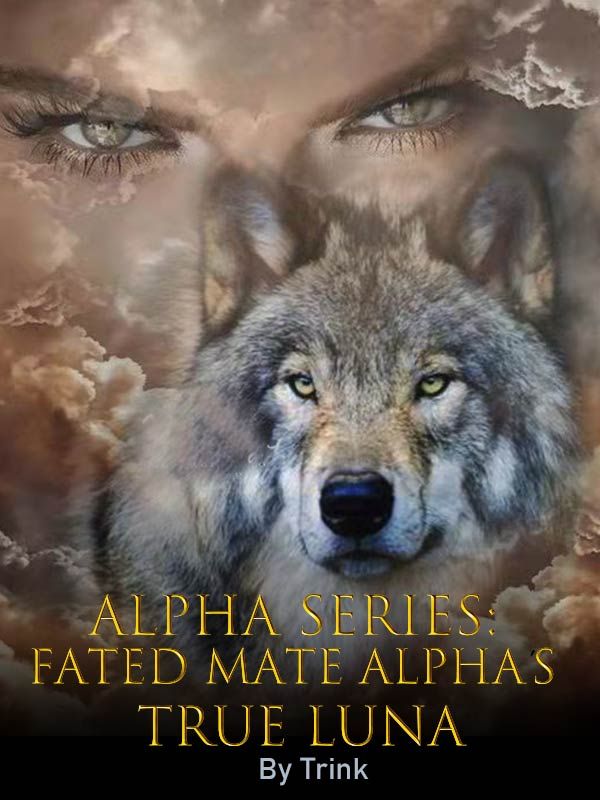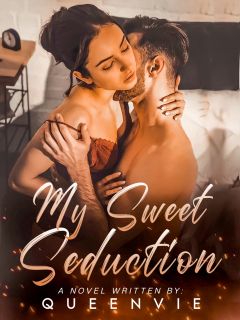
紹介
目次
紹介
マルゴーは美しく自信に満ちた女性で、最愛の婚約者、レスターがいました。
しかし、誰もレスターが結婚式から逃げ出すとは予想していませんでした。
もしかしたら、彼は交通渋滞に巻き込まれたのかもしれないし、車の故障で道端に立ち往生したのかもしれません。
理由は誰も知りません。レスターはただ、このように姿を消したのです。
ウェディングドレスを着替える時間もなく、マルゴーは車に乗り込み、花婿を探しに戻ろうとしました。しかし、彼女の車はハンサムな男性、ローレンスに止められました。
ローレンスは重要な会議に出席することを急いでいました。しかし、彼はこの泣いている美女に惹かれました。
周りの人々は皆、ローレンスが逃げ出した花婿だと思い、ローレンスにマルゴーと結婚するように説得しました。
さて、ローレンスは肩をすくめてニヤリと笑いました。
「逃げ出した花嫁さん、泣かないで。僕はあなたの元婚約者よりずっといい男だよ。」
もっと読む
すべての章
目次
第1章
第3章
第6章
第7章
第8章
第11章
第12章
第13章
第14章
第15章
第16章
第17章
第18章
第19章
第20章
第21章
第23章
第24章
第25章
第26章
第27章
第28章
第30章
第31章
第32章
第33章
第34章
第35章
第36章
第37章
第38章
第40章
第41章
第42章
第44章
第45章
第46章
第47章
第48章
第49章
第50章
第51章
第54章
第55章
第56章
第57章
第58章
第59章
第61章
第63章
第64章
第65章
第66章
第67章
第68章
第70章
第72章
第76章
第77章
第78章
第79章
第80章(終わり)
第2章
第60章
第10章
第22章
第39章
第4章
第9章
第52章
第74章
第5章
第53章
第69章
第73章
第75章
第71章
第43章
第62章
第29章